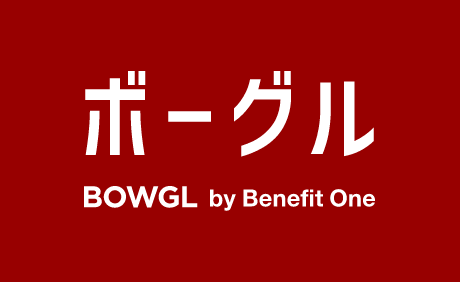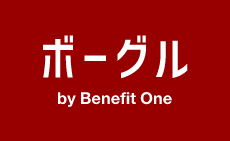会社の5Sとは?安全で快適な職場環境を整える活動内容と導入方法を紹介

従業員のワークライフバランスを実現しながら組織内のコミュニケーションの活性化などを目的に、オフィス出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークを導入する企業が増えています。オフィス出社の頻度がコロナ禍以前よりも減ったのは間違いないですが、毎日出社していた時期は、オフィスで使用する文房具などの道具の場所や機器の使い方に慣れていたものの、出社する頻度が減るとそれらも忘れがちですよね。
また、近年は、在宅勤務時の業務効率化を目的としたデータ活用が推進されていますが、データや書類の内容によってはやむを得ず紙媒体のままにしておくものもあることでしょう。ハイブリッドワークで出社する頻度が低下すると、やはり書類がある場所がすぐに思い出せず見つけるまでに時間と労力がかかります。
今回、紹介する「会社の5S」という活動は、導入すると劇的に職場環境が変化し、業務効率が向上するといわれています。それでは、5Sとは何か、具体的な内容と効果が得られる導入方法について説明します。
非公開: 健康経営、うまく実践できていますか? 健康経営とは、従業員の健康管理を経営課題として戦略的に取り組む経営手法のことです。 しかし、健康経営は効果が見えにくく、担当者の負担だけが増える一方に思われがちです。 そこで、健康経営にはどのようなメリットがあるのか、特に健康経営が必要な企業の特徴を挙げ、取り組みの手順をまとめました。 健康経営銘柄や健康経営優良法人と言った顕彰制度の申請方法についても掲載していますので、理想的な健康経営を実現しましょう。
従業員が健康であれば高い集中力を保って仕事に取り組めるため、生産性が向上するというプラスのサイクルが生まれます。
会社の5Sとは?

5Sの定義
「会社の5S」とは、以下5つの項目をローマ字にした際の頭文字「S」のことで、無駄を排除し、職場環境について抱える課題を解決するための改善活動のことです。
整理(Seiri)
整頓(Seiton)
清掃(Seisou)
清潔(Seiketsu)
躾(Shitsuke)
5Sが生まれた背景
5Sを最初に実施した企業には諸説ありますが、世界的自動車メーカーのトヨタが発祥という説が有力です。昭和30年代に無駄を排除し、生産効率を向上させることを目標にトヨタが生み出した「必要なものを、必要なときに、必要な分だけ」を供給する仕組みを意味する「ジャストインタイム」は良く知られていますが、その方式の一環として5Sが導入されたといわれています。なお、「5S」というワードは、昭和40年代になって呼ばれるようになったといわれています。
5Sの目的
5Sを導入する一番の目的は、トヨタがこの活動を開始した背景にもあるとおり無駄の排除と業務の効率化です。同時に、5Sを実践する中で職場環境が改善され、従業員のモラル向上や意識改革などの社員教育も目的とされています。5Sの対象はモノや情報だけではなく、仕事そのものや業務プロセスも含まれます。
5Sの具体的な内容

5Sの5つの「S」について、以下に具体的な内容を紹介します。また、5Sは以下のステップで導入されます。
5Sの各ステップ
|
5Sの 名称 |
アルファベット 表記 |
意味 |
| 整理 | Seiri | 必要なものと不要なものを区別し、不要なものは処分すること |
| 整頓 | Seiton | 利用頻度や業務の流れを意識して、必要なものを使いやすい場所にきちんと置くこと |
| 清掃 | Seisou |
身の回りや職場をきちんと掃除しておくこと |
| 清潔 | Seiketsu | 「整理」、「整頓」、「清掃」を意識して使いやすくきれいな状態を維持すること |
| 躾 | Shitsuke |
「整理」、「整頓」、「清掃」、「清潔」が確実におこなわれるように職場のルールや規律を守り、習慣化すること |
非公開: 健康経営に関するお役立ち資料 お役立ち資料のご案内健康経営の基礎知識と取り組みのステップを理解して
効果が出る健康経営の実現と顕彰制度の申請方法を知りたい方はまずはこちらから
5Sの効果

ここでは、5S活動を実践することで得られる効果を解説します。
職場の安全性が向上する
労働契約法第5条には、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」とあり、企業には常に従業員が健康で安全に業務遂行できるように職場環境を整備する安全配慮義務が定められています。
職場が整理整頓されていて設備点検が十分にされていれば事故を未然に防ぎ、汚れがなくきれいなことで安全衛生にも寄与します。
本来の業務に集中できる
大塚商会が実施した調査によると、ビジネスパーソンは備品や資料などの探し物をするために年間150時間もの時間を費やしているとのことです。例えば、勤務日数が年間250日だとした場合、職場で探し物をする時間は1日あたり36分になります。オフィス内の整理整頓が徹底されれば、職場にある必要な備品や資料を探す手間が省かれてコア業務に集中する時間の確保ができます。また、この時間の短縮は時間外労働の削減につながりますのでコストの削減にもメリットをもたらします。
従業員の生産性が向上する
きれいで快適な職場はメンタル面にも良い影響を及ぼし、業務に集中できることから間違いや失敗が減る傾向にあります。時間あたりの作業量についてもばらつきが減り、生産性や品質の向上が期待できます。
組織が活性化する
5S活動に取り組む部署やチームなど関係するメンバーが一致結束するためには、能力の違いや個性を尊重しながらも共通の基準やルールの策定が必要です。5Sに基づいたルールを設定して共有し、浸透していくにつれてスムーズに実践できるようになります。また、この経験から業務を進めていく上でもぶつかった課題を提起し、解決へ向けた取り組みの共有を習慣化することで認識のずれが発生しにくくなり、チームワークが向上するというメリットもあります。
クリエイティブな能力の開発に役立つ
5S活動は、自分たちが当たり前のようにおこなってきた業務を見つめ直すプロセスでもあります。何のためにその業務に取り組んでいるのか、自ら積極的に深掘りして仕事の価値を探求することで自律性と創造性を持った思考や能力を伸ばしますので、人材育成にも効果があります。
5Sの導入方法

5つの導入ステップ
5Sの導入方法や進め方はさまざまですが、今回は以下の手順で導入します。
1. 現状把握
↓
2. 計画して担当を決め、担当者間でルールを共有
↓
3. 5Sのうち、「整理」「整頓」「清掃」の3Sを優先して徹底的に実行
↓
4. 3Sを徹底することで「清潔」「躾」の2Sが自然とできるようになり、意識と行動が変化
↓
5. 活動を可視化してナレッジを共有し、改善が必要な場合は新たなルールを策定
5S導入の具体例
前項5つのステップにおける具体的なアクションを「オフィスのデスク」に当てはめてみると以下のようになります。5Sを実践することで、従業員は清潔なデスクの使いやすさを実感できるようになります。
| 1. | デスクの上のモノが整然とされていない現状を把握 |
| 2. | デスクが固定であれば各自が担当し、フリーアドレス制であればチーム単位や各部から代表者など複数の担当を決め、デスクの上を片付けるルールを共有する |
| 3. | 使用しない文房具などのモノは排除し(整理)、必要な文房具は使用頻度や業務の流れを意識して定位置を決め(整頓)、掃除を実施(清掃) |
| 4. | 3.の状態を維持する(清潔)。もし、モノがデスクの上にある場合は共有したルールに基づいて掃除を実施(躾) |
| 5. | 3.と4.の活動を記録して可視化して共有し、改善が必要な場合はルールを見直して策定したものを共有する |
5S活動を成功させるポイント
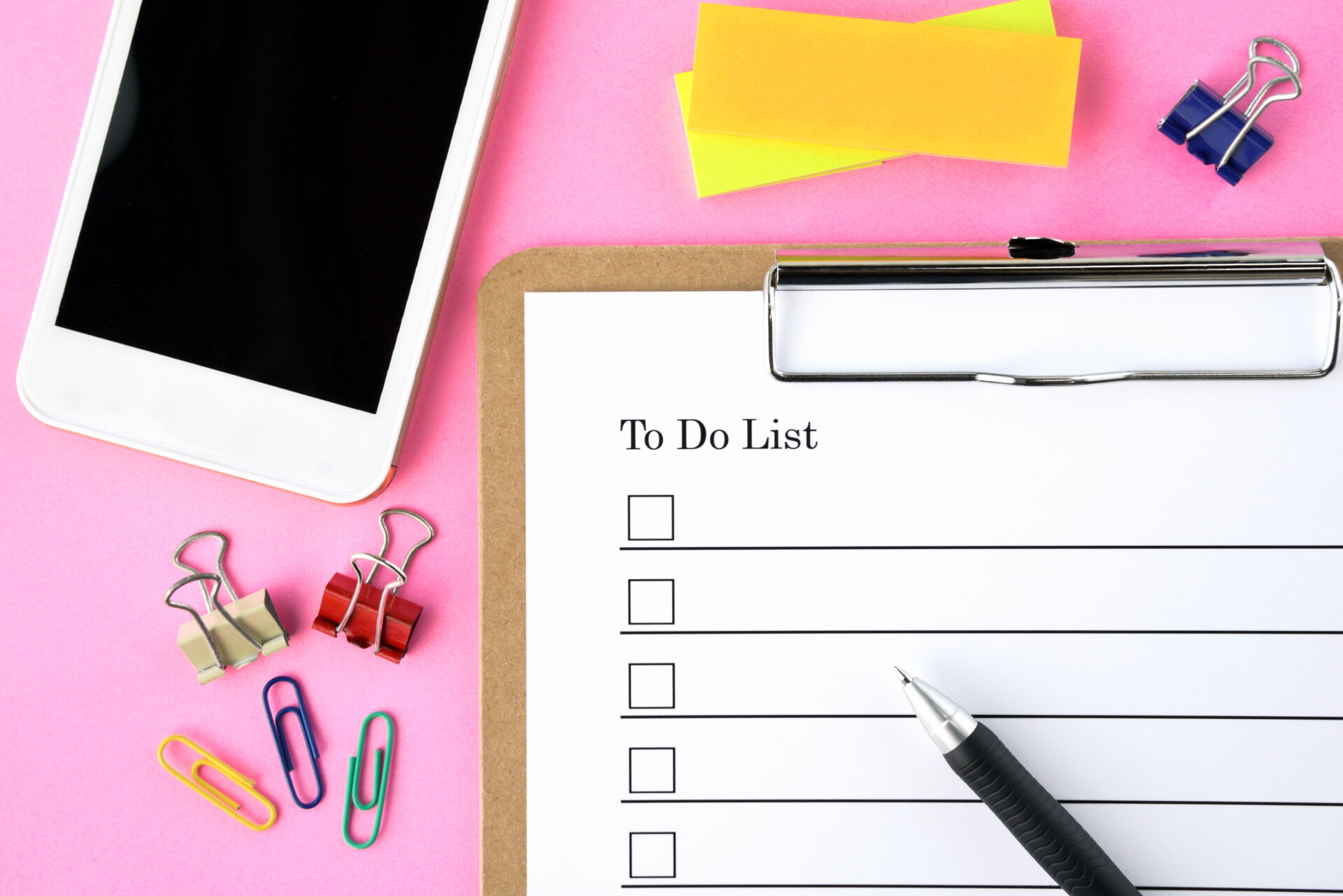
5S自体が導入の目的ではない
5Sの中には「躾」という要素が含まれていますが、5Sそのものは従業員を「躾ける」ための活動ではありません。経営者が職場の整理整頓のために5S活動を実施している場合もあります。しかし、従業員は行動や行為が目的化されると、何のために整理整頓を徹底しておこなうのか徐々に疑問を感じるかもしれませんので、経営者や5S活動を推進する担当者が5Sの意味やそれにより何を成し遂げたいのか、明確なビジョンを持ち、それを伝えることで5S活動への理解と意識の変革が重要です。
チェックシートを活用する
従業員の意識改革を実現するためには5S活動を継続することが必要です。そして、5S活動を継続するためにはルールやステップを明確にし、どの程度達成されているか可視化による確認が役立ちます。ルールに基づき実行すべきアクションを表にしたチェックシートを作成すると、達成までの進捗が可視化しやすくなります。また、複数のチームや部門で活動する場合は、それぞれの取り組みレベルを確認して可視化することも必要です。
厚生労働省が作成したチェックシートは、こちらからダウンロードが可能です。また、食品産業向けには農林水産省が作成したチェックシートがありますので、こちらからダウンロードしてください。
5S活動の改善が進まない理由を分析する
5S活動が進まない場合は、活動の目的を周知して理解の度合いを確認しましょう。前項で挙げたチェックシートに基づいて、改善が進まない理由を洗い出して分析することが効果的です。実行したものを振り返って見直し、改善点があれば改善しようとする意識と行動に変革を起こすことで成果を出す行動特性が身につきます。
【アンケート】従業員の健康に対する意識理解していますか? 効果的な健康経営を実施するためには、現状を把握したうえで、自社に適した取組みを検討することが重要です。ただ、なにから実施すればいいのかわからない方が多いのではないでしょうか?自社の現状把握はアンケートを活用しましょう。 ・健康に対して持っている意識 こういった従業員の現状を知ることで、自社に適した効果的な取組みを実施することが可能です。以下より無料でダウンロードできますのでぜひご活用ください。
・健康に対しておこなっている取組みはなにか
5S活動に取り組む企業の事例

5Sに取り組む場所は、製造業を中心とした工場や施設が多いですが、オフィスでももちろん導入可能ですので、職場環境改善と業務効率化に取り組む際の参考にしてください。
総合モーターメーカーA社
製造業のA社は、会社の売上の成長と利益の伸びを実現するため、5Sに「作法(Saho)」を加えた「6S」と「良い社員(Quality Worker)、良い会社(Quality Company)、良い製品(Quality Products)」から成る「3Q」が必要だといいます。これまでの5Sの「清潔」は、3Sをきれいな状態で維持することでしたが、A社の「清潔」は社員の身だしなみのことを指します。また、6Sで新たに加わった「作法」とは、社員のマナーや接客態度、身だしなみのことを指します。
A社では、社員1人ひとりが6Sを習得することで3Qが達成されるという理念の基で、3Q6Sを社員へ正しく浸透させ、社員それぞれのモチベーションが向上して組織が活性されることから業績も向上すると考えられています。そして、3Q6Sを浸透させるために社内の基本ソフトウェアとして導入し、現場と社員の質の向上に取り組んだ結果、高い収益を上げる企業へと成長しました。
総合物流企業B社
B社では、お客様から品質と安全について向上を要請され、5Sに加えて「しつこく(Shitsukoku)」「しっかり(Shikkari)」の2Sを追加し、「7S活動」の推進を実施しています。7Sを導入したことで、安全面ではリスクや事故の可能性が低減、品質面では作業員の意識改善による正確性とサービスが向上、コスト面ではジャストインタイムに通じるような「必要なものを、必要な時に、必要な数量購入」する習慣が身につきました。
例えば、「整頓」では、現場での見える化を徹底し、管理表を掲示することで整頓を継続する仕組みを「しつこく」「しっかり」構築したことで、保管している物流の品質の向上と潜在的なリスク回避につながっています。
自動車の生産・販売メーカーC社
5Sを体系化した企業であるC社では、ムダな作業の排除を徹底し、漠然と「整理」「整頓」を掲げるだけでなく、「必要な書類は10秒で取り出す」など細かなルールを設け、5S活動の各ステップにテーマを設けています。
例えば、「整理」については「いつか使う物」への対応や「都合の悪いものを隠してはいけない」、「整頓」については「使用頻度×動作経済」を原則に、5Sを意識していなくても目に留まるルールを策定するなど、ステップごとに具体的にテーマを決めているため、5S活動への従業員の理解が深まり、取り組みやすいといえます。
受託粉砕事業を営むD社
D社では、実務を意識した収納方法を実現するために以下のような5S活動を実施しました。
・広げた状態で収納していた脚立を、たたんで収納するようにした
・ペール缶に乱雑に入れていた道具を、管理用のボードに収納するようにした
・掃除機のコードを巻き付けていたが、コード収納用のフックを取り付けるようにした
これらを実施した結果、見た目がきれいに見えるだけでなく道具を保管・管理する定位置が決まることで在庫が可視化され、丁寧に道具を扱うことで故障を抑制と従業員のつまずきを防止することにつながり、そして、道具を探す時間も減り、従業員の安全性と業務効率が向上しました。
粉体ハンドリングのトータルプランナーE社
E社は2006年から5S活動の取り組みを開始し、今では5S活動を検討している組織団体が自社の取り組みからヒントを得られるように工場見学を受け付けるほど、全従業員の意識やマインドに5S活動が浸透していることがうかがえます(新型コロナウイルス対策のため現在は受付中止)。
E社がここまで5Sを徹底するようになった背景には、工場内の道具や書類が整然とされておらず、「このままで良いのか?」という疑問の投げかけからです。未整理の状況を目では見ていて整理整頓をしないといけないという意識まではあったものの、多忙を理由にこれまで行動に移せていなかったことに対してついに声をあげ、5S活動が開始しました。
E社の具体的な5S活動は、以下のとおりです。
| 整理 | 持ち込まれたテスト粉のうち、使われなくなったものや返却不能なものは処分 |
| 整頓 | 工具や事務用品を「姿置き」することで、すぐに所在がわかるように整頓 |
| 清掃 | 当番表や定期的に清掃するルールを設ける |
| 清潔 | 定期的に「5Sパトロール」、毎週月曜日の全体朝礼で「5S活動報告」を実施 |
| 躾 | 各部署から選出した委員により「生産改革委員会」を運営、「5S活動板」を設置し、問題点の洗い出しと改善の効果を表示、視覚的に把握できるようにした |
15年以上5S活動を続けている現在も改善が必要だとE社はいいますが、改善に気づけるということは、現状を正確に把握し、可視化されて全社に取り組みが共有されている証拠ではないでしょうか。
非公開: 新型コロナとインフルエンザの同時流行に備えた対策を! 新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症は、オフィス内でクラスター(集団感染)を引き起こすきっかけになりがちです。
クラスターが発生すると生産性が低下し、事業計画が正常に実行されない可能性もありますので、健康経営や安全配慮義務として感染症対策を徹底しましょう。
感染症対策の中でも、在宅勤務が実施しづらい企業ではワクチン接種が効果的です。
無料でダウンロードできる資料は下のボタンからご確認ください。
まとめ
5Sは、これまで多くの企業で導入されてきました。ただ、前述のとおり5Sは活動そのものが目的ではなく、何のためにおこなうのかを理解することが大切です。5S活動がコア業務というケースは少ないですので、取り組み内容によっては感謝の気持ちを添えてインセンティブの付与をすることも組織を活性化させて業務効率を上げる方法の1つです。
ベネフィット・ワンが提供している「インセンティブ・ポイント」は、ポイント管理システムと交換アイテムをワンストップで提供するサービスです。2022年現在、576社に導入実績があり、多様なニーズに応える約20,000の交換アイテムを備えているため、5S定着にも効果を発揮します。
5Sの取り組みを自社に浸透させるよう工夫し、職場環境の改善から業務効率化をはじめとした本格的な意識改革を目指してみてはいかがでしょうか。
社内コミュニケーションが活性化
社員のやる気を引き出すインセンティブ・ポイント

優秀な人材が辞めてしまう…
会社へのエンゲージメントが低い…
職場に活気がなく生産性が上がらない…
上記のような問題は、社員一人一人のモチベーションを向上させることで解決ができます。
モチベーションの向上は社員のエンゲージメントを高め、労働生産性の向上にもつながります。
社員のやる気を引き出すオリジナルのポイント制度”インセンティブ・ポイント”は、
・多様なニーズに合わせて、約40,000点から好きなアイテムと交換できる
・コミュニケーションが活性化され、社内環境の改善につながる
・人材定着率40%アップに成功した事例も。確実な導入効果を実感できる
すでに業界トップシェアを誇る576社が導入、404万人の社員が利用しています。
ぜひこの機会に、社員のやる気を引き出すオリジナルのポイント制度を検討してみましょう。