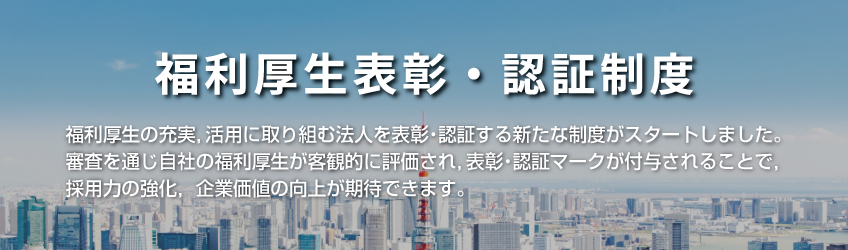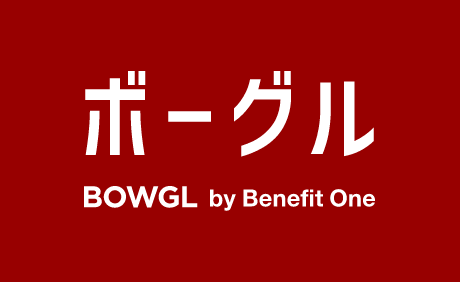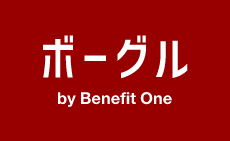ウェルビーイングとは?基礎知識から取り組み事例を解説

昨今のビジネスシーンにおいて、従業員一人一人の健康に配慮した経営が重要という気運が高まる中、注目を集めている概念がウェルビーイング経営です。
しかし、そもそもウェルビーイング経営とは何か、ウェルビーイング経営が企業にもたらすメリットは何かという問いに対し、自信を持って答えられるという方は意外に少ないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、ウェルビーイングの意味やウェルビーイング経営に企業が取り組むメリット、日本と海外におけるウェルビーイング経営の企業事例を解説します。
ウェルビーイングとは?簡単に分かる基礎知識
【3分で分かる】ウェルビーイングとは
ウェルビーイング(well-being)とは、「well(良い)」と「being(状態)」が組み合わさった言葉のことです。身体的・精神的・社会的に満たされた状態を表す概念で、広義的な意味の幸福・多面的な幸せを表します。
ウェルビーイング(well-being)の語源は、イタリア語で幸せや福祉を表す「benessere(ベネッセレ)」で、16世紀ごろから使い始められた言葉とされています。直訳すると「幸福」「健康」「福利」といった意味です。
また、厚生労働省は「雇用政策研究会報告書」において、ウェルビーイングを『個人の権利や自己実現が保障され、身体的、精神的、社会的に良好な状態にあることを意味する概念』としています。
つまり、ウェルビーイングとは、身体的にも精神的にも、さらに社会的にも、全てが満たされた状態にあることを意味する言葉といえるでしょう。
ウェルビーイングが定義された背景
「ウェルビーイング」という言葉が国際的に広く認知されるようになったのは、1946年に採択された世界保健機関(WHO)憲章で言及されたのが契機となります。憲章ではウェルビーイングを「すべてが満たされた状態」と定義しています。
Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.
「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。」」
引用:世界保健機関(WHO)憲章とは | 公益社団法人 日本WHO協会
それまでの「健康」が病気や怪我がないという身体機能的な視点で捉えられていたのに対し、WHOは「身体的・精神的・社会的に良好な状態」、つまりは心の状態や社会とのつながりを含む全てが満たされているという多面的な概念として位置づけました。
近年この定義が再び注目を集めている背景には、経済的な成長が必ずしも人々の幸福感向上にはつながらなかったという課題があります。一定の所得水準を超えると経済成長や所得の増加が幸福度の向上に与える影響が小さくなる現象は、提唱した学者の名前をとって「イースタリン・パラドックス」と呼ばれています。
主要先進国のデータを分析してみると、2012-2014年から2017-2019年の期間において、アメリカでは一人当たり実質GDP(購買力平価ベース/2021年基準)が9.07%成長したにもかかわらず、国民の幸福度(Cantril Ladderスコア)は7.10から6.91へと0.20ポイント低下していました。同様に日本でも5.77%の経済成長に対して幸福度は6.03から5.89へと0.14ポイント低下しています。
こうした事象を経てGDP(国内総生産)のような客観的な経済指標だけでは測りきれない「個人が実際に感じる豊かさや生活の質」への関心が高まり、特に成熟した先進国では物質的な豊かさから心の豊かさを重視する価値観へのシフトが進んでいるのです。
(幸福度については2013年のデータがないため、2012年と2014年の平均値を採用しています)
現代のウェルビーイングは、以下の5つの特性を持つ多面的な概念とされています。
主観的な側面
個人の人生満足度や幸福感、日々の感情といった内面的な実感を重視します。
客観的な側面
健康寿命や収入水準、労働時間、有休取得率といった統計的に測定可能な指標で評価されます。
多面的な性質
心身の健康だけでなく、仕事や学習、人間関係、地域環境など複数の領域が相互に影響し合います。
多様性の観点
個人の価値観や文化的背景によって「良好な状態」の定義が異なることを認識します。
持続的な観点
一時的な高揚感ではなく、満たされた実感が続いて日常になることを目指します。
【PERMA理論】ウェルビーイングの5つの構成要素
ウェルビーイングは、5つの構成要素(幸福を測る指標)を測定することによって表されることが一般的です。
ウェルビーイングを構成する要素については、「PERMA(パーマ)理論」と「ギャラップ社提唱の構成要素」という有名な二つの理論が提唱されています。
ここではまず、PERMAについてみていきましょう。
PERMAは、5つの構成要素(Positive emotion・Engagement・Relationship・Meaning・Accomplishment)の頭文字を取った名称です。5つの要素を最大化することで、ウェルビーイングであるかが決まります。
次項で、PERMAのそれぞれの構成要素について詳しく解説します。
P:Positive emotion(ポジティブ感情)
Positive emotion(ポジティブ感情)は、喜び・楽しみ・愛・思いやり・感謝・希望といった前向きな感情のことを指します。ポジティブな感情は、身体的・精神的・社会的な豊かさにつながるものです。
また、ネガティブな感情の影響を解消し、心身のレジリエンス(問題対処や回復力)を促します。
ポジティブな感情は、気の合う友人や好きな人とともに時間を過ごしたり、趣味に興じたり、創造的な活動に挑戦したり、ワクワク感やインスピレーションを与えてくれる音楽を聴いたりすることで高められます。
E:Engagement(物事への関わり)
Engagement(エンゲージメント)は、何かしらの物事や活動に、時間を忘れて夢中になっていることを指します。いわゆる「ゾーン」や「フロー」と呼ばれる状態に入ることです。
「フロー」という用語を生み出した心理学者のミハイ・チクセントミハイ氏は、「幸せとは、遊びの感覚で夢中になれるものがあること」としています。幸せになりたければ、時間を忘れて夢中になったり、集中していることにすら気づかないほど没頭できたりする何かを見つけることと、それ自体を楽しめる何かに取り組むことが大切だと説きました。
仕事や趣味などに没頭し、その状態を楽しむことができれば幸福度が上昇し、その間はネガティブな感情に浸ることがなくなるため、ストレスが軽減されるとされています。
R:Relationship(豊かな人間関係)
Relationship(リレーションシップ)は、他者と深いつながりがあって協力や意思疎通ができる状態を指します。「他者から支えられ、愛され、大切にされている」と感じられ心が満たされている状態です。ここでいう他者とは、配偶者や家族、友人、同僚、コミュニティなどを指します。
心理学者のクリストファー・ピーターソン氏の言葉に、「幸せにおいて、他者は大切である」というものがあります。この言葉は、他者との関わりやつながりが幸福度に大きな影響を与えるという意図です。
社会的なつながりは、幸福感や満足度、自己肯定感を高めます。親しい間柄や身近な間柄の人とのつながりであれば、幸福度をより高められるでしょう。
興味のあるグループに参加したり、相手に質問をしてその人の人となりを知ろうとしたり、疎遠になっている友人などと連絡をとったりすることで、リレーションシップを高めることが可能です。
M:Meaning(人生の意義や目的)
Meaning(ミーニング)とは、長期的な人生の意味や目的です。人生に対して肯定的な意味や目的を見つけられるかどうかは、幸福を高めるために欠かせません。
精神科医であり心理学者でもあるヴィクトール・フランクル氏の言葉に、「人間が欲しているのは、幸福ではなく、幸福になる理由である」というものがあります。幸せになるには、人生の意味や目的が必要というものです。
人生に意味や目的を持っていれば、仕事やコミュニティ活動などから「自分が生きる意味」を見出し、幸福感を得られやすくなります。また、人生の意味や目的があれば行動の軸がぶれないため、苦境を乗り越えられる可能性もあるでしょう。
新しい活動をしてみたり、ボランティアなどで他者に奉仕してみたり、大切な人と時間をともに過ごしたりすることで、ミーニングを高められます。
A:Accomplishment(達成感)
Accomplishment(アカムプリッシュメント)は、自分がやろうと思った目標や目的を成し遂げることです。
「自身の成長」といった内発的な目標を達成することは、「お金や名声」といった外発的な目標を達成することより、大きな幸福を得られます。目標を達成することで、自分に自信がつき自己効力感も高まるでしょう。
また、自分の過去の成功体験を振り返ったり、目標の達成時には自分で自分を褒めたりすることでもアカムプリッシュメントを高めることは可能です。
【ギャラップ社】ウェルビーイングの5つの構成要素
続いて、アメリカの世論調査研究所であるギャラップ社が提唱するウェルビーイングの5つの構成要素について、詳しく解説します。
Career well-being(キャリア ウェルビーイング)
Career well-being(キャリア ウェルビーイング)は、仕事や、家事・育児・勉強などのプライベートも含んだキャリアの幸福度です。仕事において自分の能力・実績が正しく評価されているかだけでなく、生活全体でワークライフバランスが保たれているかも幸福には重要なことです。
ビジネスの側面からいうと、仕事でのキャリア構築とあわせて、プライベートのバランスも適切に維持されていることで幸福度を高められます。
イギリスの雑誌「The Economic Journal」の調査によると、長期間失業を経験した方(特に男性)の場合、5年経過しても幸福度が失業前の状態まで回復しなかったと報告されています。
全ての人がそうとはいい切れませんが、仕事に就けていること自体が幸福度に影響を与えていることがわかります。
Social well-being(ソーシャル ウェルビーイング)
Social well-being(ソーシャル ウェルビーイング)は、人間関係に関する社会的な幸福度です。
具体的には、配偶者や家族、友人、同僚、コミュニティなどの周囲の人と良好な人間関係を構築できているかを指します。ビジネスにおいていえば、上司や同僚と良好な信頼関係を築けているかどうかがSocial well-beingに関係します。
Social well-beingの幸福度には、接する時間の多さだけでなく、信頼、敬意や愛情で結ばれている人間関係であるかも重要です。なぜなら、我々は人とのつながりから喜びや信頼、愛情などを受けて満足することで幸せを感じるからです。
そのため、人生において強固な人間関係があることや、親しい友人がいることが幸福度を高めるというSocial well-beingの考え方です。
トム・ラースとジム・ハーターによる著書「Wellbeing: The Five Essential Elements」によると「充実した1日を過ごすためには、6時間の社交的な時間が必要だ」とするデータも報告されています。それほど、人間関係は幸福度に深く関わる要素なのです。
Financial well-being(フィナンシャル ウェルビーイング)
Financial well-being(フィナンシャル ウェルビーイング)は、経済的な幸福度のことです。以下のような内容が、構成要素の尺度となります。
- 収入(報酬)を得る手立てがあるか
- 収入(報酬)に納得しているか
- 満足のいく生活がおくれているか
- 資産管理ができているか
など
つまり、自分の経済状況に満足し、安心して生活していることで感じられる幸福です。
また、他者のための寄付によってお金を使うことや物を買うことでも、フィナンシャル ウェルビーイングは向上するといわれています。
実際にハーバード大学の研究チームの調査によると、調査対象者に少額のお金を渡し、その日の夕方までに全額を使うように指示したところ、自身のためにお金を使った人より、他人のためにお金を使った人のほうが幸福度が向上したという結果がでています。
Physical well-being(フィジカル ウェルビーイング)
Physical well-being(フィジカル ウェルビーイング)は、心身の幸福度です。自分がしたい行動を不自由なくできる健康状態を理想とします。
ビジネスでいえば、心身ともに健康で、仕事に対する高いモチベーションを維持して仕事に従事できるかどうかを指します。
フィジカル ウェルビーイングは、適度な運動や良質な睡眠によって高めることが可能です。
実際に、トム・ラースとジム・ハーターによる著書「Wellbeing: The Five Essential Elements」においても、20分間程度の運動でも運動終了後に数時間気分を改善できることが明らかになったとする実験データも報告されています。
Community well-being(コミュニティ ウェルビーイング)
Community well-being(コミュニティ ウェルビーイング)は、地域や家族、職場などの自身が所属するコミュニティに貢献している実感で得られる幸福度です。自分が周囲の人とつながっている感覚や帰属意識、コミュニティに影響を与えている感覚などにより幸福を感じるというものです。
例えば、献血により社会貢献を考えている方を対象とした調査では「献血の前後で気分が高揚した」とする実証結果も報告されています。
コミュニティは、ビジネスでいえば会社や部署、取引先といった企業内、企業間の関係だけでなく、地域社会や国際社会に対して、企業とそこで働く人々が良い影響を及ぼし、貢献するためのプロジェクトが含まれます。
コミュニティに貢献したり参加したりすることは、Community well-beingが高まるだけでなく、自身の能力や自信向上にもつながるでしょう
ウェルビーイングとウェルフェア・ウェルネス・ハピネスの違い
ウェルフェアとの違い
「ウェルビーイング(well-being)」が一般的な幸福・健康と訳されるのに対し、元々医療や福祉の分野で使われる言葉である「ウェルフェア(welfare)」は、一般的に「福祉・福利・幸福・繁栄・福祉事業・生活保護」などと訳されます。
ビジネスにおいて、ウェルフェアという言葉は主に福利厚生の意味で使われることが多いでしょう。
ウェルビーイングは、どちらかというと「目的」として使われ、ウェルフェアは「手段・方法」として使われることが一般的です。
ウェルネスとの違い
「ウェルネス(wellness)」は、英英辞典では以下のように定義されています。
「the state of being in good health, especially as an actively pursued goal(積極的に目標とする健康な状態)」
ウェルネスが、「身体的・精神的に健康な状態」であるのに対して、ウェルビーイングは身体的・精神的な健康に加えて、社会的にも満たされた状態です。
ウェルネスよりもウェルビーイングのほうが、より多面的な幸福であることがわかります。
ハピネスとの違い
ハピネス(happiness)は、英英辞典によれば「the state of being happy(幸せな状態)」を指す意味の言葉で、一般的に幸福・満足・喜び・幸運・幸せなどと訳されます。
ウェルビーイングもハピネスも幸福な状態を表しますが、言葉の使い方が異なります。
ハピネスは、単一的かつ感情的で瞬間的な幸せを指して使われることが多い言葉です。一方、ウェルビーイングは、より持続する幸せを意味します。
日本におけるウェルビーイング
ウェルビーイングが注目される背景
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)はメインテーマに「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲げ、2025年6月20日~同年7月1日まで「健康とウェルビーイングウィーク」をテーマに「一人ひとりのウェルビーイングが共鳴する社会をどう実現するか?」について考え直す31のプログラムが展開されました。
また、東京ビッグサイトや幕張メッセ、大阪で定期的に開催されている総合展示会『Business Innovation Japan』では、『ウェルビーイングEXPO』『働き方改革Week』など複数の専門分野に特化した展示会を同時に開催。ウェルビーイングが経営の重要なテーマのひとつになっていることが伺えます。
ウェルビーイングが社会的なテーマになる背景には、複合的な社会構造の変化が挙げられます。
新型コロナウイルスの蔓延を契機として、メンタルヘルスの問題や密を避けることによる孤独・孤立、デジタル格差が社会全体の課題として顕在化。少子高齢化による人手不足、地域コミュニティの運営も深刻化し、働く人だけでなく、高齢者や子育て世代、学生など、あらゆる世代でウェルビーイングの低下が深刻な社会問題と認識されました。
特に若年層を中心に収入だけでなくプライベートな時間やつながりを重視する価値観が広がり、従来の働き方や生活様式の見直しが求められてきたのです。
このように社会全体でウェルビーイング向上への機運が高まる中、企業においても単なる福利厚生を超えた経営戦略としてウェルビーイングへの取り組みが不可欠となっています。人材獲得競争の激化と労働力不足が深刻化する現在、ウェルビーイング経営は企業が持続的に成長していくための重要な基盤といえるでしょう。
ウェルビーイング経営による企業のメリット
ウェルビーイング経営による企業のメリットとして、以下の3つがあげられます。
- 重要員の満足度が高まり業績向上につながる
- 従業員の離職率改善が見込める
- 優秀な人材の確保につながる
従業員の満足度が高まり業績向上につながる
アステリア株式会社の調査によると、積極的にウェルビーイングの向上に取り組んでいる企業は、そうでない企業と比べて、3年前と比較した利益成長率が約2倍以上になるという結果が報告されています。
ウェルビーイングが良好な企業では、従業員の心身が健康に保たれることでやりがいを感じ、意欲的に業務に取り組みます。
調査結果にもあるように、ウェルビーイング経営が結果として、生産性向上や企業業績向上にもつながるのです。
ウェルビーイングへの取り組みは、企業の成長にとって欠かせない重要な要素となっていくでしょう。
従業員の離職率改善が見込める
経済産業省の「健康経営度調査」によると、健康経営度が高い企業の離職率は全国平均より低い値となっています。
ウェルビーイングが良好な企業は、従業員のエンゲージメントや定着率が高い傾向にあり、離職率改善にもつながっているといえるでしょう。
また、ウェルビーイングに取り組んでいる企業では、労働環境が整えられたうえで、適度な対話や多様な働き方が認められることから、離職理由につながる従業員の不満がでにくいと考えられます。
良質のウェルビーイングを維持することで、総合的な企業力も高められるのです。
優秀な人材の確保につながる
従業員を大切にし、労働環境が整った企業は、就職先として魅力的な存在です。離職率が低いことで、外部からは長く勤めたくなる魅力がある企業と評価されるでしょう。
「ウェルビーイングに積極的に取り組み、地域社会や国際社会に貢献している企業である」という前向きなイメージは、企業のブランド力を向上させ、優秀な人材確保にもつながります。
そのため、ウェルビーイングに積極的に取り組む企業だと求職者に認知されれば、企業文化に共感した優秀な人材が確保しやすくなるでしょう。
ウェルビーイングの測定方法
ウェルビーイングの効果的な測定には、主に「自社アンケートの実施」と「専用ツールの活用」という2つのアプローチがあります。
アンケート調査による測定
自社でアンケートを実施する場合、仕事と私生活の両面から幸福度を評価する質問項目を設計しましょう。
効果的な調査を行うためには、調査目的を明確に伝えたうえで匿名での回答とし、結果が人事評価に影響しないことを保証する必要があります。従業員の本心をヒアリングできなければ意味がありません。
質問設計では、「全く満足していない」から「非常に満足している」までの5段階から7段階のリッカートスケール(段階的な選択肢)を採用し、中央値を設けることで回答者の心理的負担を軽減できます。また、前の質問が次の回答に影響を与えないよう、重要な項目を連続させない順序設計も重要です。
質問文は特定の回答を誘導しないよう中立的な表現を心がけ、先に触れたPERMA理論(モデル)やギャラップ社が提唱する要素、OECDの指標を参考に項目を選定して網羅性を高めると良いでしょう。
専用ツールの活用
ウェルビーイング測定に特化したツールを用いれば、専門性と信頼性を担保しながら手間とコストを抑えることができます。代表的なツールとして、慶應義塾大学との共同開発による「幸福度診断Well-Being Circle」があり、72問のアンケートで34項目のウェルビーイングチェックを実施できます。
また、海外で開発された「PERMA診断」は、PERMA理論に基づいて開発された無料で利用可能なツールです。ただし、日本語版では個人を特定できる情報を除き、開発した金沢大学にて受検データを研究目的で利用することが明示されていますので、企業で利用する場合は注意が必要です。
これらのツールは、ブラウザ上での手軽な実施・自動集計機能・個別フィードバックの提供などの特徴を持っており、継続的な測定による変化の追跡も容易になります。
継続的な測定と改善
ウェルビーイング測定は定期的に実施して効果を検証し、PDCAサイクルを回すことが重要です。一回だけの結果で良し悪しを判断するのではなく、結果を具体的な改善策につなげることでウェルビーイングが向上していきます。
データで分かる「日本のウェルビーイングの今」
世界幸福度ランキング2025における日本の現状
2025年版世界幸福度報告書において、日本は147カ国中55位という結果でした。
幸福度を構成する6要素を詳しく見ると、日本は「健康寿命」で世界2位、「1人当たりGDP」で34位と経済・健康面の客観的指標では上位に位置しています。しかし、「人生選択の自由度」が83位、「寛容さ(経済力に比べて寄付しているか)」が131位と主観的な幸福度に関わる指標では大幅に順位を下げており、これが総合順位を押し下げる主な要因となっています。
2021年の世界幸福度報告書でも、「向社会的(または助け合い)行動はパンデミック以前の多くの研究で幸福度を向上させることが示されている社会的行動の一種」と言及されています。
見知らぬ人への援助は147位と最下位、寄付行動は131位、ボランティア活動は104位(いずれも147ヶ国中)と、日本では自発的には誰かのために行動を起さないという結果が出ており、「自発的に誰かのために行動することは幸福度向上に寄与する」と実証されたと報告されていることを踏まえると、幸福感は得られにくくなっています。
また、同報告書では食事回数と幸福度の関係にも言及。誰かとともに食事をする回数が増えれば、主観的な幸福度が上がると結論づけています。
これらのデータから、日本の幸福度向上には「つながり」と「思いやり」の社会的基盤が不可欠といえるでしょう。
企業として行える施策は、従業員同士の交流機会の創出・社会貢献活動への参加支援・職場での食事環境の整備など。社員食堂やランチプログラムの充実、ボランティア休暇制度の導入、部門横断的なコミュニティ活動の促進などは、従業員の幸福度向上だけでなく人材確保・定着・労使関係改善の戦略的投資としても重要性を増しています。
※参照: World Happiness Report 2025 https://www.worldhappiness.report/
※参照:Chapter 2 Statistical Appendix https://files.worldhappiness.report/WHR25_Ch02_Appendix_B.pdf
内閣府による「満足度・生活の質に関する調査」
日本でも従来のGDPのような経済指標では捉えきれない国民の主観的ウェルビーイング(幸福感や生活の質)を定量的に測定し、証拠に基づく政策立案(EBPM)に活用する動きが見られます。この調査は「経済成長が必ずしも国民の幸福度向上に直結しない」という現代的認識のもと、多面的な生活の質を把握し、真に国民の幸福度を高める政策の方向性を見出すことを目指しています。
調査の最も重要な目的は、国民一人ひとりが自身の生活をどのように感じているかを主観的な視点から把握し、政策の優先順位付けや効果検証に活用すること。OECD(経済協力開発機構)の「より良い暮らし指標(Better Life Index)」の枠組みに準拠することで国際比較可能な調査として設計されており、グローバルなウェルビーイング研究への貢献も重要な目的となっています。
2022年~2024年の3年間は、新型コロナウイルス感染症からの回復期として、国民のウェルビーイングに重要な変化をもたらしました。2022年は「長引く感染症下で定着した社会活動変化」、2023年は「家族構成、将来不安、仕事への意識」、2024年は「働き方と満足度の関係、重視事項と評価事項」に焦点を当てた分析が実施されています。
直近3年間のデータを見ると、日本人の生活満足度は着実に改善しており、2022年の5.76点から2023年には5.79点、2024年には5.89点と調査開始以来の最高水準を記録しました。
企業が特に注目すべきは、満足度を左右する主要要因。「生活の楽しさ・面白さ」「家計と資産」「健康状態」が上位3つとなっており、従業員が重視する分野で実感を得られると全体満足度が大きく向上することが判明しています。
また、働き方やワークライフバランスに関しては以下のような記述が特に目を引きます。
- 2022年…仕事時間や通勤時間の減少がWLB(ワークライフバランス)満足度の向上に寄与
- 2023年…仕事への主観的意識(やりがい等)が客観的条件(雇用形態や年収)以上に満足度に影響
- 2024年…副業の可否や有無ではなく「自らが望む働き方の実現」できているかどうかが重要
これらのデータは、給与やベアなどの条件だけでなく健康支援・スキル向上・家計サポート・つながりの場など、多面的に福利厚生を充実させることの重要性を示しています。
※参照:【PDF】満足度・生活の質に関する調査報告書2022 https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/manzoku/pdf/report06.pdf
※参照:【PDF】満足度・生活の質に関する調査報告書2023 https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/manzoku/pdf/report06.pdf
※参照:【PDF】満足度・生活の質に関する調査報告書2023 https://www5.cao.go.jp/keizai2/wellbeing/manzoku/pdf/report06.pdf
日本・海外企業のウェルビーイング取り組み事例
日本国内の事例
トヨタ自動車株式会社
【業種:自動車製造/売上高:48,036,700百万円(2025年3月現在)/従業員数:71,515人(2025年6月現在)】
トヨタ自動車株式会社は、ウェルビーイング経営に留まらず、ウェルビーイング社会の実現を目標としています。
生産台数や販売台数などの営業目標を守るだけでなく、企業として社会に貢献することを目標とし、アクションしていくと宣言しています。
【取り組み事例】
- 年に一度のストレスチェックを実施
- 機関紙などを通じたヘルスリテラシー向上の情報発信
- 時間外労働の減少
- 育児や介護休業からの復職率の上昇
など
トヨタ自動車株式会社のウェルビーイングは、まず幸せを追求し、その結果として営業成果がついてくるという考えに基づいています。
株式会社丸井グループ
【業種:その他の投資業/売上高:4,926,855百万円(2025年3月現在)/従業員数:4,051人(2025年3月現在)】
株式会社丸井グループでは、ウェルビーイングの専門部署として「ウェルネス推進部」を設置し、従業員の心身の健康を保ち活力を増進させるため、以下の取り組みを実施しています。
【取り組み事例】
- 組織活性化プログラムの実施
- ストレスチェックの結果をもとに施策を実施
- メタボ率改善プログラム
- メンタル状態を支援する講座
など
社会や将来世代にとって意義のある仕事に挑戦し、成長を続けることで全てのステークホルダーの「しあわせ」を実現するといった働き方の実現を目指しています。
楽天グループ株式会社
【業種:他の事業サービス/売上高:2,279,233百万円(2025年3月現在)/従業員数:29,097人(2025年3月現在)】
楽天グループ株式会社では、CWO(Chief Well-being Officer)のリーダーシップのもと、健康をサポートする事業を担当する「ウェルネス部」、従業員と企業のつながりを高める「サスティナビリティ部」、情報発信などを担当する「エンプロイーエンゲージメント部」の部署を設置しています。
【取り組み事例】
- 社内設備(カフェテリア・昇降式デスク導入・社内フィットネスジム・マッサージ・針治療など)
- コレクティブ・ウェルビーイング(共通の目的のために多様な個人がつながったチーム)
- コレクティブ・ウェルビーイングを推進するツールの提供
- 三間(さんま)の推奨(仲間・時間・空間のそれぞれ適度な余白を保つ)
など
楽天健康宣言 「Well-being First 」のもと、安全な職場づくりや従業員の心身の健康にコミットし、従業員や地域社会のウェルビーイング向上を目指しています。
海外の事例
Google LLC(グーグル)
【業種:インターネット関連事業/売上高:52,502,700百万円(350,018百万米ドル)/従業員数:182,381人(2025年3月)】
Googleは、積極的にウェルビーイングに取り組んでいることで有名な企業です。
【取り組み事例】
- プロジェクト・アリストテレス:従業員の心理的安全性を保つことに着目し、職場内で誰かに何かをいったり指摘をしたりしても、ペナルティを受けないというもの
- ピアボーナス:仲間内(peer)での報酬(bonus)という意味の言葉で、従業員同士で感謝の言葉と社内ポイントを送りあうシステム
- 20%ルール:業務時間のうち20%を通常業務とは異なる業務(新規事業立案など)に充ててよい制度
Macquarie Group(マッコリーグループ)
【業種:金融サービス/売上高:1,679,555百万円(17,315百万オーストラリアドル)/従業員数:19,735人(2025年)】
Macquarie Groupでは、従業員の発想力・実行力が企業に欠かせないとものと考え、ウェルビーイングに積極的に取り組んでいます。
【取り組み事例】
- 従業員家族のサポート(育児休暇の取得推進と復帰支援など(復職率:97%)・育児センターの設置)
- 男女共同参画の促進
- LGBTQ +の人が働きやすい職場づくり
報酬や昇進などにおいて男女が平等に扱われる透明性のある仕組みをつくり、LGBTQ+であるマイノリティの人々でも働きやすいよう従業員教育を行いLGBTQ+への意識を高めています。
IKEA(イケア)
【業種:金融サービス/売上高:7,784,260百万円(45,100百万ユーロ 2025年)/従業員数:231,000人(2025年)】
IKEAでは、「多様性やジェンダーの平等性は、優れたアイデアやサービスの源泉になるものである」として、ウェルビーイングに取り組んでいます。
【取り組み事例】
- 男女共同参画の促進
- LGBTQ+スタッフとの協働
理事会などのメンバーを男女で平等な配分にし、男女機会均等を推進しています。また、店舗のある半数以上の国で男女の同一賃金を採用するだけでなく、性的指向・性同一性に関係なく働ける職場環境づくりを行っています。
今から始める「企業のためのウェルビーイング」ガイド
労働人口の減少と人材獲得競争の激化により、企業の人事戦略は根本的な転換期を迎えています。離職率改善・優秀な人材確保・良好な労使関係の構築といった課題に対し、従業員のウェルビーイング(心身・社会・経済の総合的な幸福感)向上への取り組みは、理想論ではなく企業の競争力を左右する重要な経営戦略となってきました。
・コミュニケーション環境の構築
職場内の風通しがよく、従業員同士で気軽にコミュニケーションをとることができる環境は、ウェルビーイングの基盤となります。定期的な研修やワークショップの実施、従業員が自然に交流できるオープンスペースの設置により、職場内の信頼関係を醸成することができるでしょう。
テレワーク(リモートワーク)環境では、バーチャルランチ会や定期的な雑談タイムなどを用意。物理的距離による孤立感を解消し、チームの一体感を促しましょう。
・包括的な健康支援体制の確立
従業員の心身の健康はウェルビーイング実現の土台となります。健康診断や予防接種といった基本的な取り組みに加え、産業医との個別面談、ストレスチェックの実施、メンタルヘルスケアサービスの提供が必要です。
従業員が健康を維持することができれば、結果として生産性の向上と医療費の削減につながります。これを健康経営といい、昨今では力を入れている企業が増えています。
・柔軟な働き方を実現する制度設計
長時間労働の是正、フレックスタイム制やリモートワークの導入、充実した休暇制度の整備、休日を満喫できるようなサービスなどによって、従業員のワークライフバランスを実現することが重要になってきます。
必要なサービスは従業員のライフステージごとに異なるため、一律ではなく多岐に渡る環境整備を進めて人材の定着率向上を目指しましょう。
・ライフステージに応じた包括的サポート
出産や育児、介護といったライフイベントの際も従業員が安心して働いていくためには、託児所の設置やベビーシッター・家事代行サービスの利用補助、介護支援制度の充実など、負荷を軽減できるような福利厚生が求められます。 出産や育児のための休暇制度は法定でもありますが、利用しやすい環境でなければ意味がありません。加えて、制度だけでなくお互いにサポートしあえる雰囲気を作っておくことも大切です。
福利厚生、ウェルビーイング向上への投資は単なる人件費の増加ではありません。優秀な人材を集め、長く働いてもらい、仕事の効率を上げるための大切な投資です。
充実した福利厚生制度は、「この会社は従業員を大切にしている」という明確なメッセージとなり、求職者にとって魅力的な会社として映ります。その結果、他社との差別化を図り、優秀な人材を獲得できるという強力な武器となりえます。
従業員が心身ともに満たされて働けるようになると、個人の幸福感が高まるだけでなく、職場全体のやる気や一体感が向上します。新しいアイデアが生まれやすくなり、最終的には会社の持続的な成長につながる良い循環が生まれるでしょう。
従業員を第一に考える経営こそが、変化の激しい現代において企業が選ばれ続けるための重要な鍵となるのです。
福利厚生でウェルビーイングを促進!企業事例集
大成温調株式会社
大成温調株式会社は、従業員のウェルビーイング促進とエンゲージメント向上を目指し、「コミュニケーション費」の支給と福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」の導入を軸とした施策を展開しています。
コミュニケーション費は部署単位で活用され、日常的な対話や懇親、現場連携など、社員同士の相互理解や創意工夫を促進。コロナ禍で一時中断されたものの2022年度から再開され、職場の風通しや信頼関係の醸成に寄与しています。
一方、2016年導入のベネフィット・ステーションによって、従来関東圏に偏っていた福利厚生の地域格差を解消し、全社員が平等に多様なサービスを利用できる環境を整備。月に1回のチラシ掲示やアプリリニューアルを通じた周知徹底により、利用率は前年比11.9%向上しました(2024年)。
これらの施策は、社員のプライベート充実や健康増進、ワークライフバランスの実現、さらには会社への帰属意識や採用力の向上にも波及。総務部は「従業員=お客さま」という意識のもと従業員とその家族も含めた支援体制を強化し、「この会社に入ってよかった」と思われる職場づくりに継続的に取り組んでいます。
ユーソナー株式会社
ユーソナー株式会社は「みんなが親孝行できる会社」をビジョンに掲げ、従業員の【健康・お金・時間】の3つの余裕を生む福利厚生を体系的に展開しています。
健康面では平日ランチの無料提供や外部専門家との面談制度、お金の面では書籍代補助(技術書では全額、ノンフィクションでは半額)やAIによる評価、360度評価制度の導入、時間の面では通勤距離に応じた家賃補助(最大50%)や長期休暇制度を実施しています。さらに、社員の声を改善に活かす「デマンド経営」も特徴的です。
同社がベネフィット・ステーションを導入した決め手は、二親等まで利用可能な点が親孝行というビジョンに合致したこと、そして会社規模拡大に伴う多様化するニーズへの対応力でした。導入後は社員が各自のニーズに合わせてサービスを積極的に活用、既存制度との相乗効果により、総合的なウェルビーイング向上を実現した好例といえます。
株式会社セールスフォース・ドットコム
株式会社セールスフォース・ドットコムは、4つあるコアバリューの中で特に重視している「カスタマーサクセス」を従業員にも適用、従業員を”社内のお客様”と位置づけています。人事部門を「Employee Success」(社員の成功)と称するのも特徴的。社員や顧客、関係する全ての人たちをOhana(ハワイ語で「家族」の意)の一員として手を伸ばして助け合う社風があります。
従業員の健康維持とリフレッシュをサポートする「ウェルビーイング補助」では、スポーツクラブやジム・マッサージ・ダイエットカウンセリングといった従業員の個人的な取り組みに対し、月額1万円を補助。さらに、自社システムを活用して福利厚生制度の利用状況を継続的に分析し、データに基づいた改善を実施しているのも特徴的です。
従業員を顧客として捉える発想と実践的な健康支援によって高い従業員エンゲージメントを実現し、2019年・2020年・2022年に「働きがいのある会社ランキング」大規模部門で1位、2021年・2023年・2024年・2025年には2位獲得という成果につながりました。「4つのコアバリューがあるから迷わない」という社員の声もあり、会社にOhanaカルチャーが浸透していることが伺えます。
企業のウェルビーイング促進はベネフィット・ワンにお任せください
人手不足が深刻化する中、優秀な人材の採用・定着は企業の最重要課題です。株式会社マイナビの「マイナビ 2025年卒 学生就職モニター調査」によると、実際に就職先選択で5年連続「待遇(給与・福利厚生等)」が最も重要視されており、「福利厚生制度の充実」が採用力強化の鍵となっていることが分かります。
ベネフィット・ワンの「ベネフィット・ステーション」は、健康支援から日常生活・余暇支援まで140万件以上のサービスで従業員のウェルビーイングを実現する、業界最大級の福利厚生サービス。会員数1,220万人、約18,100団体の導入実績(2025年4月時点、福利厚生、CRMおよびパーソナルの合計会員数)があり、多くの企業・団体からご支持いただいています。
福利厚生でウェルビーイングを促進するメリットのひとつは、投資対効果の高さです。賃上げでは社会保険料や税金が差し引かれるため、月2,000円賃上げしても社員の年間受益は約1.8万円ですが、同額のプラン料金で利用できるベネフィット・ステーション(総合福利厚生サービス)では5~10万円相当の価値を提供できます。
実際に導入している企業からは「従業員のワークライフバランスが改善し、離職率を大幅に低減できた」「心身の健康維持により生産性とエンゲージメントが向上した」「多様なライフステージに対応した支援により、新規人材へのアピール力強化と企業イメージ向上を実現できた」というお声をいただいています。
離職率改善や人材獲得でお悩みの人事・総務のご担当者様がおられましたら、ぜひベネフィット・ワンへご相談ください。貴社の従業員一人ひとりが心身ともに満たされ、日々の仕事に充実感を感じられる「ウェルビーイング」な職場環境の構築を、最適なプランのご提案を通じて強力に支援いたします。
総合福利厚生サービス ベネフィット・ステーション

ベネフィット・ステーションは、従業員満足度を向上し、健康経営やスキルアップを促進する総合福利厚生サービスです。
グルメやレジャー、ショッピングだけでなくeラーニングや介護・引っ越しなどライフイベントに関わるものまで、
140万件以上のメニューを取りそろえています。
さらに
・Netflixが見放題のプラン
・お得な特典や割引がついた給与天引き決済サービス
などをご用意しています。