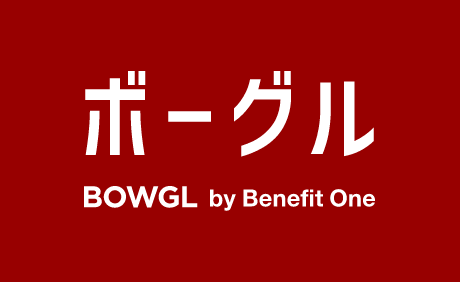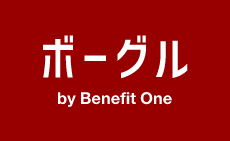【令和版】エンゲージメントとは?企業向けガイド【事例アリ】

ビジネスにおいて、よく見聞きする「エンゲージメント」という言葉。その意味や測定方法、高め方を正しく理解している方は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、エンゲージメントの意味をはじめ、指標・測定方法や向上させるための施策についてご紹介します。「従業員エンゲージメントを高めたい」とお考えの企業担当者向けに企業事例もご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
【10分で分かる】企業が知るべき「エンゲージメント」とは

エンゲージメント(engagement)とは、約束や婚約、誓約などを意味する言葉で、ビジネスでは「企業と従業員・顧客の深いつながり」を示しています。従業員が企業の理念やビジョンに共感し、義務や強制ではなく自ら会社に貢献したいと思う気持ちや行動のことで、離職率の改善や人材獲得の強化、労使交渉といった課題を解決するための土台となってくるのが「従業員エンゲージメント」です。
企業における2つの「エンゲージメント」とは
企業経営において重要なエンゲージメントには、「従業員エンゲージメント」と「顧客エンゲージメント」の2つがあります。どちらも企業が成長し続けるためには不可欠な要素です。
従業員エンゲージメント
従業員エンゲージメントとは、従業員の企業に対する愛着(企業理念・ビジョンへの共感、貢献意欲、帰属意識など)のこと。具体的には、「企業と従業員が二人三脚で同じ未来を描けているか」を示す指標のことです。たとえば、従業員エンゲージメントが高い場合は、従業員が企業に対して貢献意欲・帰属意識を持っている状態だといえます。
なお、従業員エンゲージメントの概要や高める方法については、以下の記事で詳しくご紹介しています。ぜひ、あわせてご覧ください。
従業員エンゲージメントとは?メリットや高める方法・事例を紹介
顧客エンゲージメント
顧客エンゲージメントとは、消費者が企業や商品・サービスに抱く愛着や深いつながりのこと。顧客エンゲージメントが高いというのは、「他社より高くてもこの会社の商品を選びたい」「友人にも勧めたい」という気持ちの高まりや、実際にリピート購入したり友人に紹介したりしてもらえる状態を表しています。
エンゲージメントの高い顧客は継続して購入してくれる傾向が高まるため、顧客が生涯にわたって企業に与える価値(LTV)が上がり、口コミで新しい顧客を増やしてくれるため、企業の収益性も高まります。
実務では、NPS(友人へどのくらい推奨する意欲があるかを測定する指標)や継続率、既存顧客の紹介で実際に購入や問い合わせに至った新規顧客の割合、コミュニティへの参加度などを用いて貢献度を測定し、商品やサービスの改善、顧客対応の見直し、ファンを増やす取り組みに活用します。
従業員エンゲージメントと似た用語との違い
ワークエンゲージメントの違い
「従業員エンゲージメントとワークエンゲージメントは同じもの」とお考えの方もいるかもしれませんが、それは誤りです。似て非なるものなので、その違いを正しく理解しておきましょう。
従業員エンゲージメントは、上述のとおり「企業と従業員が二人三脚で同じ未来を描けているか」を示す指標です。企業理念・ビジョンへの共感、貢献意欲、帰属意識など、さまざまな要素を含みます。これに対しワークエンゲージメントは、各従業員の仕事に対する肯定的な心理状態を指す言葉であり、主に仕事への意欲を表します。
なお、ワークエンゲージメントについては以下の記事で詳しくご紹介しています。ぜひ、あわせて読んでみてください。
ワークエンゲージメントとは?高めるメリットや方法、要素を解説
ロイヤリティとの違い
ロイヤリティは「企業に対する忠誠心・愛社精神」を指し、上下関係に基づく受動的な献身の色合いが強い概念です。企業からの期待に応える・規律を守るといった従順さが中心で、双方向の関係を築くことや自律的に改善しようと思うことまでを含むとは限りません。
従業員エンゲージメントは、企業の理念・ビジョンへの共感を前提に、従業員が「自ら価値を創出したい」という能動的な姿勢や相互の信頼関係までを含んだ用語です。現代では転職が一般化して企業が「選ばれる側」となったため、一方的な忠誠を求めるだけでは優秀な人材の獲得・定着が困難になっています。企業も従業員の価値観を尊重し、成長機会を提供する双方向の信頼関係が重要とされています。
従業員満足度との違い
従業員満足度は給与・福利厚生・労働環境など「待遇への満足」を測る概念であり、満足していても自発的に貢献するとは限りません。例えば、待遇に満足していても「言われたことだけをやる」という受動的な働き方にとどまるケースもあります。
従業員エンゲージメントは、満足に加えて『仕事の意義』『組織への共感』『推奨意向(eNPS)』といった行動につながる心理・態度までを包含します。モチベーションエンジニアリング研究所と慶應義塾大学の共同研究では「エンゲージメントスコアが向上すると営業利益率や労働生産性も上がる」という結果が出ており、単に満足度を改善するだけではなく、エンゲージメントを指標として継続的に改善に取り組むことが重要であると報告されています。
※eNPS(Employee Net Promoter Score):従業員が「この会社を友人に勧めるか」を0~10点で評価する指標
モチベーションとの違い
モチベーションは個人の「やる気」という一時的に上下する心理状態を指し、ボーナス支給や表彰、新プロジェクト開始、目標達成といった外的報酬や環境の変化に影響されやすい特徴があります。
一方、従業員エンゲージメントは企業理念への共感や上司・同僚との信頼関係といった長期的な結びつきと、「業務改善を自ら提案する」「部門を超えて協力する」「後輩の育成に積極的に関わる」といった自律的な貢献意欲を含む、より持続的な関係性の指標です。
一般的にはモチベーションは日々の出来事に左右されやすく、エンゲージメントは企業との関係性を基盤とするため相対的に安定しやすいと考えられています。ただし、組織の大きな変化があればエンゲージメントも短期で変動することがあります。
組織コミットメントとの違い
組織コミットメントは「この会社に残りたい」という気持ちを測る概念です。残りたい理由は「転職すると損だから残る」(継続)、「義理や責任感で残るべきだと思う」(規範)、「会社や仲間が好きだから残りたい」(情緒)と大きく3つに分かれます。主に定着意向を把握するのに適していますが、改善提案や部門を超えた協働といった能動的な貢献行動までを直接測るわけではありません。
従業員エンゲージメントはこうした「残りたい」気持ちに加えて、「会社をもっと良くしたい」「自分から積極的に貢献したい」という前向きな意欲と行動まで含む、より包括的な概念です。
【まとめ】従業員エンゲージメントと類似概念の違い
| どんな状態か | どんな質問で測るか | 具体的な現れ方 | |
|---|---|---|---|
| 従業員エンゲージメント | 企業と従業員が二人三脚で 同じ未来を描けているか 双方向の関与 |
仕事を通して成長できたか、 自分の仕事に誇りはあるか、 友人に会社を勧めたいか |
改善提案をする、 困難でも前向きに取り組む |
| ワークエンゲージメント | 仕事へ前向き、 意欲をもって 取り組めている |
活力・没頭・熱意 | 仕事に夢中になる、 集中して取り組む |
| ロイヤリティ | 会社への忠誠心・ 愛社精神 上下の関係性 |
会社への好意、帰属意識 | 会社の方針に従う、 長く勤める意思 |
| 従業員満足度 | 待遇や職場環境への満足 | 給与・福利厚生・環境など 待遇への満足度 |
待遇に満足、 不満は少ない |
| モチベーション | その時のやる気 | 目標達成への意欲、 やる気レベル |
目標に向けて頑張る、 競争心を発揮 |
| 組織コミットメント | この会社に 「残りたい」気持ち |
定着したい意向、 会社への一体感 |
転職を考えない、 会社目標に同調 |
従業員エンゲージメントが高まる・下がると企業はどうなる?
従業員エンゲージメントの高さは、人材の採用しやすさや従業員の定着率、仕事の生産性からサービスの品質、顧客満足度、そして最終的な売上や利益まで幅広く影響します。エンゲージメントが上がれば好循環が、下がれば悪循環が起きるため、企業経営の根幹に関わる重要な要素だといえるでしょう。
ここでは、その具体的なメリットとデメリットを整理します。
従業員エンゲージメントを高めるメリット

では、従業員エンゲージメントを高めることには、どのようなメリットがあるのでしょうか。
従業員のモチベーションが向上する
従業員エンゲージメントが高まると企業に対する貢献意欲もアップするため、自ずと従業員のモチベーションが向上します。熱意をもって取り組むだけでなく、より効率的に業務を遂行できるよう知恵を絞るようになるので、生産性の向上、ひいては業績の向上が期待できます。
生産性が向上する
このほか、生産性の向上も従業員エンゲージメントを高めるメリットのひとつです。現に、モチベーションエンジニアリング研究所と慶應義塾大学が行った研究の結果を見ると、エンゲージメントは労働生産性にプラスの影響をもたらすことがわかります。具体的には、エンゲージメントスコアが1ポイント高まると、労働生産性(指数)が0.035上昇したそうです。
参照:慶應義塾大学との研究結果を公開~エンゲージメントスコアの向上は営業利益率・労働生産性にプラスの影響~|MOTIVATION CLOUD
離職率が低下する(定着率の上昇)
従業員エンゲージメントが高いということは、すなわち従業員が企業に対して愛着を持っているということです。具体的には、企業理念・ビジョンに共感していたり貢献意欲・帰属意識が高かったりするので転職する理由がなく、結果として離職率が低下します。
従業員エンゲージメントが下がるデメリット
エンゲージメントが低下すると、まず優秀な人材から辞めていく傾向があります。新しい人を採用するコストが上がるだけでなく、新人が戦力になるまでの時間やベテラン社員がもっていた経験・ノウハウの損失も重なり、実際にかかる費用は予想以上に膨らんでしまう可能性もあるでしょう。
エンゲージメントが低下している状態では、残った従業員も必要最低限の業務だけをこなす「静かな退職」の状態になりがちで、改善提案や他部署との連携も停滞する傾向にあります。お客様対応ではマニュアル通りの機械的な対応が増えて柔軟性が失われ、サービス品質にばらつきが生じたり苦情が増えたりするでしょう。管理面では細かい監視や承認が必要になり、意思決定のスピードが遅くなります。
こうした状況が続けば、売上(利益)・ブランド力の両方が長期的に悪化していくのです。
【まとめ】従業員エンゲージメント水準による企業への影響
| エンゲージメント高(メリット) | エンゲージメント低(デメリット) | |
|---|---|---|
| 人材定着 | 離職率が下がり、優秀な人材が長く働く | 離職率が上がり、 特に優秀な人材から辞めていく |
| 生産性 | 自発的な改善で効率が向上し、生産性が上がる | 最低限の仕事のみで、 生産性とチーム士気が低下 |
| 採用力 | 社員紹介が増加し、企業ブランドが向上 | 採用・育成コストが増大し、 候補者体験が悪化 |
| 顧客対応 | 質の高いサービスで顧客満足度が向上 | 機械的な対応が増え、 苦情増加で顧客が離れる |
| イノベーション | 改善提案が活発で新しいアイデアが生まれる | 提案が減少し、 変化への抵抗で競争力が低下 |
| 企業文化 | 健全な組織風土で協働が促進される | 組織の活力が低下し、 学習機会が減少 |
従業員エンゲージメントの要素
実務では、従業員エンゲージメントを2つの側面で考えると施策を設計しやすくなります。ひとつは「物的エンゲージメント」で、給与・制度・設備など働くための土台を整えること。もうひとつは「心的エンゲージメント」で、仕事のやりがいや上司・同僚との信頼関係を築くことです。どちらか一方だけでは効果が長続きしないため、両方をセットで整備することが重要です。
物的エンゲージメント
給与・賞与・手当といった処遇、福利厚生制度、柔軟な働き方、研修などの成長機会、育児・介護支援など、就業の基盤に対する納得・充足を指します。離職を抑止する土台であり、物的施策が十分でないと心的エンゲージメントの施策の効果が表れにくくなります。
設計の要点は次の3つです。
- 公平性:他社と比べて公平な待遇か、正規非正規で不当な格差はないか
- 利用しやすさ:従業員が実際に利用しやすいか、制度は周知されているか
- 多様性に対応:育児・介護・学び直しなど人生の各段階で変化に合わせて活用できるか
近年では、総合福利厚生サービスを活用して従業員の多様なニーズに効率的に対応する企業が増えています。包括的なサービスを導入すれば、個別に制度を構築するよりもコストを抑えながら幅広く支援することが可能となるでしょう。
心的エンゲージメント
心的エンゲージメントとは、「この仕事には意味がある」「この職場は信頼できる」と感じながら前向きに働ける状態を指します。具体的には、仕事の目的への共感・上司や同僚との信頼関係・適切な裁量と自律性・成長している実感・公正な評価・安心して意見を言える雰囲気・チームで助け合える関係といった、日々の働く体験の質が中心となります。
設計の要点は次の5つです。
- 目的と方向の共有…会社の目標と日々の仕事を結びつけて伝える(定期的な目標確認、成果の意味づけ)
- 関係の質を高める…上司・同僚との信頼関係を築く(定期1on1、建設的フィードバック、適切な称賛)
- 公正さと見通し…評価基準を明確にし、キャリアの選択肢を示す(基準の公開、昇格要件の明文化)
- 自律性の確保…役割と裁量をはっきりさせ、段階的に任せる(権限の明確化、委譲の段階設計)
- 心理的安全性…意見や失敗を学びに変える環境をつくる(発言の歓迎、失敗の共有文化)
物的エンゲージメントが整っていると、これらの取り組みが効果を発揮しやすくなり、従業員が自ら積極的に企業に貢献する原動力につながります。
従業員エンゲージメントが注目される背景
なぜ今、従業員エンゲージメントが企業経営の重要テーマになっているのでしょうか。労働環境と働く価値観の大きな変化など、背景には以下のような要因があります。
働く価値観の多様化
高収入や昇進を重視する従来の価値観から、やりがい・成長・柔軟性・公正さを重視する価値観へと変化しています。終身雇用の前提が弱まり、転職が当たり前になったことで、企業は「選ばれ続ける職場」であることが必須になりました。特に若い世代ほど、企業を選ぶ基準として「働きがい」「成長機会」「企業の社会的意義」を重視する傾向が強くなっています。
労働力不足と採用競争の激化
少子高齢化により労働力人口が減少し、人材の確保が困難になっています。採用コストは上昇し、採用期間も長期化する傾向にあります。優秀な人材を獲得・定着させるためには給与などの条件面だけでなく、働く環境や成長機会、企業文化の魅力を高めることが重要です。
リモートワークと働き方の変化
コロナ禍を契機としたリモートワークの普及により、物理的に離れて働くことが一般化しました。上司が直接見守ることができない環境では、「指示されたから仕事をする」のではなく、「会社の目標に共感し、自分から積極的に取り組む」従業員でないと成果が出にくくなりました。そのため、従業員の自発的な貢献意欲を引き出すことが重要になり、従業員エンゲージメントが注目されるようになってきています。
事業環境の不確実性(VUCA時代)
VUCA(ブーカ)とは、変化が激しく予測困難な現代の事業環境を表す言葉です。このような環境では、現場での素早い判断や部門を超えた協働、従業員からの改善提案が競争力を決めます。指示待ちではなく、自ら考えて行動する従業員を増やすためにはエンゲージメントの向上が不可欠となり、従業員エンゲージメントが注目されるようになりました。
※Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)
労使交渉における共通言語の必要性
従来、処遇や福利厚生の拡充は「コストがかかる」という理由で後回しにされがちでした。しかし、優秀な人材の獲得・定着競争が激化する中で、労働組合も企業も「従業員の働きやすさが企業競争力に直結する」ことを認識するようになりました。そこで、福利厚生や成長支援への投資効果を客観的に測定して「将来のリターンを生む戦略的投資」として説明できる指標の必要性が高まり、eNPSや継続勤務意向などの指標によって投資対効果を数値で示すことができる従業員エンゲージメントが注目されるようになってきています。
このように、人材が企業の競争力の中核となった現代において、従業員エンゲージメントは採用・定着・生産性・イノベーションをつなぐ重要な軸となっているのです。
エンゲージメントの指標と測定方法

ここでは、エンゲージメントの指標と測定方法について解説します。
エンゲージメント総合指標
エンゲージメント総合指標とは、従業員が今の企業に対してどういう想いを抱いているか、どのような評価を下しているのかを把握するための指標です。「eNPS(Employee Net Promoter Score)」「総合満足度」「継続勤務意向」の3つで構成されています。
|
eNPS |
自分が勤めている企業を友人や知人に勧めたいかどうか |
|---|---|
|
総合満足度 |
総合的な観点から、今の企業にどのくらい満足しているか |
|
継続勤務意向 |
今の企業で今後も継続して働きたいか |
エンゲージメントレベル指標
エンゲージメントレベル指標とは、どれほどの熱意を持って仕事に取り組んでいるかを把握するための指標です。以下の3つの要素にフォーカスした「UWES(Utrecht Work Engagement Scale:ユトレヒト・ワーク・エンゲージメント尺度)」という調査項目のもと指標を測ります。
|
熱意 |
仕事に対してやりがいや価値を感じるか |
|---|---|
|
没頭 |
意欲的に仕事を行うことができるか |
|
活力 |
楽しみながら仕事をし、生き生きと働けるか |
具体的な質問には、たとえば「自分の仕事に価値を見出していますか?」「仕事をしていると時間の流れを早く感じますか?」などが挙げられ、従業員には5段階で回答してもらいます。
エンゲージメントドライバー指標
エンゲージメントドライバー指標とは、最終的に従業員エンゲージメントを高める要因になる指標です。「組織ドライバー」「職務ドライバー」「個人ドライバー」の3つで構成されています。
|
組織ドライバー |
職場環境や人間関係など、企業(組織)と従業員の状態 |
|---|---|
|
職務ドライバー |
従業員が取り組む業務の難易度 など |
|
個人ドライバー |
各従業員の資質が実際の業務にどう影響を及ぼすか |
顧客エンゲージメントの指標と測定方法
顧客エンゲージメントは、顧客のリアルな声を収集・確認できる「アンケート」を利用して測定するのが効果的です。また、その際は「NPS(ネットプロモータースコア)」を指標とします。
NPSとは、顧客の企業や商品・サービスに対する愛着度(顧客ロイヤリティ)を測る指標です。0〜10の11段階のスコアを用意し、顧客にその中のひとつを選んでもらうことで愛着度を判断します。
具体的には、「この商品・サービスを友人や知人にどの程度おすすめしたいですか?」などの質問に対し、顧客に11段階のスコアで答えてもらいます。そして、その回答結果をもとに顧客をカテゴライズしていきます。0〜6を選んだ顧客は「批判者」、7〜8を選んだ顧客は「中立者」、9〜10を選んだ顧客は「推奨者」と区別しましょう。
ここまで終えたら、すべての回答を集計し「推奨者の割合」から「批判者の割合」を引いてNPSを導き出します。たとえば、推奨者が50%・批判者が20%ならNPSは30になります(50-20=30)。
推奨者が多いほど、そして批判者が少ないほどNPSの数値は高くなるため、この点を踏まえながら商品やサービスの開発・改善に取り組むことが大切です。
従業員エンゲージメントの指標と測定方法
従業員エンゲージメントも、主にアンケートを利用して測定します。質問内容には、たとえば「この1年間、仕事を通して成長できましたか?」「自分の仕事に価値や誇りはありますか?」「自分が勤めている企業を友人や知人に勧めたいですか?」などが挙げられます。
顧客エンゲージメントを測定する際のアンケートとの相違点は「顧客の回答方法」です。顧客エンゲージメントを測定する際のアンケートが11段階評価だったのに対し、従業員エンゲージメントを測定する際のアンケートでは10段階評価、または自由記述で回答します。
従業員エンゲージメントを測定する際の指標は、「エンゲージメント総合指標」「エンゲージメントレベル指標」「エンゲージメントドライバー指標」の3つです。詳しくは後述します。
日本の「従業員エンゲージメント」のいま
株式会社アジャイルHRが実施した『【第3回】全国1万人エンゲージメント調査結果レポート』によると、日本の従業員エンゲージメントは改善した昨年(2024年)から一転して低下に転じており、継続的な対策の必要性が示されています。
※このレポートでは従業員エンゲージメントを、仕事を通じて得られるポジティブな心理状態である” ワークエンゲージメント”と所属する会社や組織に対する思い入れや愛着心として” 組織コミットメント”が合わさったものとしています。
そうだ(4)、ややそうだ(3)、やや違う(2)、違う(1)から回答。ポイント合計を回答者数で割って全体のスコアとしています。
全体水準と推移
従業員エンゲージメントの平均スコアは2.54で、前年よりも0.05ポイント下がりました。3ヵ年推移では2023年→2024年→2025年でワークエンゲージメントは2.64→2.68→2.64、組織コミットメントは2.41→2.49→2.45と推移。「一時的な改善後、再び低下している」と分析されています。
属性別の状況
従業員規模別で50人未満の企業は2.63とスコアが比較的高いのですが、100~299人では2.41と低い状況。年代別では30代の組織コミットメント落ち込み幅が前年比で-0.21と顕著で、上司と部下の間で板挟みになりやすく、ライフイベントが重なる年代が不安を抱きやすいのではないかと推察されています。
雇用形態別に見ると、最高値の正規雇用役員の組織コミットメントは2.94、最低値は派遣社員で2.15となっています。
働き方別の傾向
リモートワークとオフィス出社の割合が同程度の従業員が2.78と最高スコア。完全リモート勤務では仕事の意義や役割の明確さを示す仕事レベルの資源が高い(3.11)一方で、上司や同僚のサポートがポイントとなる職場レベルは2.36、経営層との信頼関係や公正な人事評価を表す会社レベルは2.35と相対的に低く、同僚との協力関係や人事評価の透明性が課題であることが伺えます。
2025年の調査結果で従業員エンゲージメントが下がったことは、現状のままでは改善が期待しにくく、なお従業員のエンゲージメントを高める努力が必要であることを示唆しています。特に30代の組織コミットメントの低さ・会社レベルの資源の低さ・企業規模や雇用形態間の格差などに注意が必要です。
従業員エンゲージメントを向上させるには
従業員エンゲージメントを高める4つの方法
各従業員の価値観を知る
同じ企業で働いていても、「仕事を第一に考えたい」「プライベートを優先させたい」などと人によって価値観は異なります。この場合、企業は全体的なバランスを確認しながら、従業員一人ひとりが働きやすい職場環境を作らなければなりません。そうすることで従業員が企業に対して愛着を持つようになり、エンゲージメントが向上するのです。
そのため、まずは定期的に1on1ミーティングをしたりアンケートを実施したりして、従業員の価値観を把握する必要があります。
なお、1on1ミーティングについては以下の記事で詳しくご紹介しています。実施するメリットや効果測定方法について解説しているので、ぜひあわせてご覧ください。
1on1ミーティングが気になる方へ。成功させるための効果測定方法と必要なスキル
マネジメント層に対して教育を実施する
企業のマネジメント層には、部下となる従業員の意欲や知られざる能力を引き出す役割があります。これこそがまさに従業員エンゲージメントの向上につながる要素であり、マネジメント層のサポートによって従業員の意欲・向上心が高まれば、自然と企業に対して愛着を持てるようになります。そのため、企業としてはマネジメント層に対してコーチングやフィードバックに関する教育(=マネジメント研修)を行うことが大切です。
なお、マネジメント研修の内容や陥りがちな問題とその解決法については、以下の記事でご紹介しています。ぜひ、あわせて読んでみてください。
コミュニケーションが取りやすい環境にする
従業員エンゲージメントを高めるには、コミュニケーションが取りやすい環境にすることも大切です。従業員同士、頻繁にコミュニケーションを取るようになると安心感が芽生えるため、企業や上司に対する信頼感が高まりやすくなるといえます。
もし、リモートワークにより対面でのコミュニケーションが困難な場合は、チャットツールでこまめに連絡を取り合ったりWebミーティングを実施したりといった工夫を施しましょう。
なお、企業におけるコミュニケーションのポイント・取り方については、以下の記事でご紹介しているのであわせてご覧ください。
社内コミュニケーションはなぜ必要か?メリットや取り組み事例を紹介
リーダーシップを評価する
このほか、リーダーシップのある従業員を評価することも欠かせません。なぜなら、リーダーシップのある従業員がいれば、その周りの従業員の能力を最大限に発揮しやすくなり、生産性やエンゲージメントが高まりやすくなるためです。評価システムなどを活用して、リーダーとして活躍する人材を適正に評価しましょう。
従業員エンゲージメントを高めた企業事例
ドリームビジョン
IT関連事業を展開するドリームビジョン株式会社は、「日本一エンジニアにやさしい会社」を掲げて従業員エンゲージメントの向上に継続的に取り組んできた結果、ハタラクエール2022で優良福利厚生法人(部門賞:福利厚生への熱意)を受賞し、2023年から現在(2025年)まで福利厚生の充実、活用に意欲のある法人(福利厚生推進法人)の認証を受け続けています。
同社の大きな特徴は、創業時から未経験者採用に力を入れ、多くの未経験入社者が一人前のエンジニアとして活躍している点です。これを支える仕組みとして、書籍購入補助や資格取得支援といった成長支援に加え、ウェルカム休暇やアニバーサリー手当、懇親会費補助などの生活・関係性支援を組み合わせています。これらの包括的なサポートにより、未経験者は「会社が自分の成長を支援してくれている」という実感を継続的に得られ、一人前のエンジニアになるまでの長期間にわたって高いモチベーションと組織への愛着を維持できていると考えられます。
制度運用面では、2022年6月に採用・教育・評価を一気通貫で担うHRM事業部を新設し、毎年行っている社員アンケートに基づいて制度をブラッシュアップし続けています。また、選択肢が豊富な福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を2015年から導入し、担当者が自らフィットネスクラブを体験してレポートするなど具体的な利用方法を丁寧に案内して利用促進を図っています。
このような多角的な支援体制の結果として社員からは喜びの声が多数聞かれており、離職率の大幅な改善も確認されています。また、未経験者が一人前のエンジニアとして活躍できるまで成長を支援する体制は、担当者によると「採用面でも一定の効果がある」とされ、同社の従業員エンゲージメント向上を支える重要な基盤となっています。
ワールドコンストラクション
建設業で多岐にわたるソリューションを提供する株式会社ワールドコンストラクションは、人材獲得競争が激化する中、従業員エンゲージメントを軸にした人材戦略で、新卒採用を従来の年間約80名から2024年は150名へと87.5%増を実現しました。福利厚生の充実・女性活躍支援・SNS発信という複数の軸で採用力を強化しています。
福利厚生面では、賞与や社員持株会、確定拠出年金、引っ越し費用全額負担などの制度を充実させ、ベネフィット・ステーション(BS)も導入。導入3か月で半数超の社員が利用しており、求められていたサービスであったことが伺えます。映画の鑑賞料金の割引、ベビーシッターや保育サービスの入会金が無料または割引になったり、BS上から申し込みをすると介護サービス利用料が割引されたりするなど、全国どこの地域にいても身近に利用できるサービスが豊富に用意されている点が、多拠点展開する同社の社員満足度向上に大きく寄与しています。
女性活躍支援では、建設関連の事務業務を請け負うBPO部署を新設。リモートワークで作業できるため、育児や介護などのライフステージに応じて長く働き続けられるような環境を整備しました。
SNS戦略ではInstagramで約10,000人のフォロワーを獲得し、社員参加型の情報発信を推進。実際に社員間の良好な関係に魅力を感じて入社する新卒者も現れており、企業認知度の向上に貢献しています。
その結果、日本マーケティングリサーチ機構が実施した調査で「未経験でもキャリアアップできる」「社員の意見を大切にしてくれる」「待遇・福利厚生が充実している」の3部門でNo.1を獲得。企業魅力度の向上が応募者の拡大と志望度向上を促し、採用力強化の成功事例となっています。
※参考:日本マーケティングリサーチ機構「建設系アウトソーシング事業会社についてのインターネット調査」, (2024年1月15日~2024年2月20日) https://jmro.co.jp/r01535/
広島トヨペット
広島トヨペット株式会社は、福利厚生制度の見直しにより従業員エンゲージメントを高め、2024年度の新卒離職率0%という画期的な成果を達成しました。
同社は従来、山口県にある保養施設の利用や人間ドックの受診を福利厚生として提供していましたが、保養施設は他県にあるため利用率が低く、人間ドックは若手社員の利用が少ないという課題がありました。そこで、より多くの社員が活気に満ちて活動できる環境を整えることが会社の発展につながると考え、「全社員が平等に利用できる福利厚生」を目指し、幅広い世代が活用できるベネフィット・ステーション Netflixプランを新たに導入しています。
Netflixの利用率は92%(2025年2月末時点)。導入時の全社員説明会での告知や、月1回の社内メールによる継続的な情報発信も奏功し、社員からは「会社の福利厚生でNetflixが視聴できるのは嬉しい」「ベネポ(システム内で利用できるポイント)をWAONやnanacoポイントに交換して活用している」「楽天トラベルでベネポと楽天ポイントが両方たまってお得」といった喜びの声が寄せられているほか、eラーニングを受講して日々の業務に生かす社員もいるようです。
充実した福利厚生は採用活動においても大きな効果を発揮しており、担当者によれば「会社説明会でベネフィット・ステーションを紹介すると学生からの反応も良い」とのこと。結果として新卒離職率0%を初めて達成したこの取り組みは、全社員が公平に利用できる福利厚生の提供、Netflixという話題性の高いサービスの提供が従業員満足度向上と人材定着・離職率の抑制に直結することを示す好例といえます。
はとバス
観光バス事業を主力とする株式会社はとバスでは、社員の定着とスキルアップを目指し、社員同士の交流活性化と一体感の醸成を通じて従業員エンゲージメントの向上に取り組んでいます。
同社は希望制による社員旅行を復活させ、運転士・バスガイド・整備士・事務職といった異職種間の交流機会を創出しました。この取り組みによって普段接することのない社員同士の仕事理解が深まり、その後の業務連携が円滑になるという効果が生まれたといいます。
特に効果的なのが、年一回配布される「ファミリーサマーチケット」。社員とその家族がはとバスの企画旅行や定期観光を無料で楽しめるこのチケットは、毎年9割以上の高い利用率を誇ります。あるバスガイド社員は「両親に『楽しかったよ』『上手だったよ』と言われると、非常にやりがいを感じる。はとバスにいるからこそできる親孝行」と語っており、家族の前で自分の仕事を披露できる体験が会社への誇りと愛着を強めています。
さらに、通年利用可能な福利厚生としてベネフィット・ステーションを導入。年5000ベネポの付与とWEBサイト・アプリでの利便性向上により社員の関心を引きつけ、労働組合の福利厚生部による周知ポスターの作成などにより制度の浸透を図っています。
社員旅行の復活、ファミリーサマーチケット、そしてベネフィット・ステーションといった多様な福利厚生施策により、『他の職種の同僚も現場で頑張っている』という共有意識が生まれて社員の愛着心やエンゲージメントが向上し、会社全体の一体感醸成と組織パフォーマンスの向上を実現しています。
大成温調
建設業界で80年以上の歴史をもつ大成温調株式会社(従業員約580名)は、「円滑な人間関係の構築と風通しの良い職場づくり」を目指し、コミュニケーション費の支給とインセンティブポイントの活用により従業員エンゲージメントの向上を実現してきました。
コミュニケーション費による交流の活発化では、部署単位で予算を支給して社員間の相互理解とコラボレーション機会の創出に取り組んでいます。コロナ禍による中止期間を経て、2022年度に再開。近年多くの企業で課題となっている社内コミュニケーション不足の解決に向け、各部署がそれぞれ工夫を凝らして予算を活用することで、職場内の連携強化が進んでいると言います。
他にも、従業員の貢献や社内イベントへの参加などに応じて付与され、感謝の気持ちとともに贈り合えるインセンティブポイント制度を導入し、積極的な参加を促進しています。従業員からは「ポイ活感覚で楽しい」「スポーツジムやレストラン等に使えて選択肢が広がった」との声が挙がっており、特に繁忙期の部署間協力ではポイントを通じた感謝の循環が生まれています。
この2つの施策の相乗効果が心理的安全性と一体感を高め、従業員が主体的に関わる風土の醸成や「この会社に入ってよかった」と感じられる環境づくりなど、従業員エンゲージメントの向上に大きく寄与したとのことです。
物的・心的、ともにエンゲージメントを上げられる【福利厚生】に注目
従業員エンゲージメントは物的(処遇・制度)と心的(信頼関係・やりがい)の両輪で高まりますが、労働力不足と採用競争が激化し働く価値観が多様化する現代において、福利厚生は両面に同時にアプローチできる戦略的な投資として注目されています。
企業が「選ばれる側」となった今、優秀な人材の獲得・定着には「給与以外の価値提供」が不可欠なのです。
福利厚生とエンゲージメントの関係
福利厚生の充実は、従業員エンゲージメントに多面的な効果をもたらします。住宅手当や通勤手当、健康保険といった基本的な制度によって生活基盤が安定し、安心して業務に集中できる物的エンゲージメントの土台が築かれるのです。
一方、育児支援やeラーニング、リフレッシュ休暇などは「会社が自分を大切にしている」という実感を生み出し、企業への所属感や信頼関係を深める効果をもたらします。ベター・プレイス社の調査では、福利厚生が充実していると「エンゲージメントが向上する」と約8割(77.9%)が回答し、転職時も約8割(79.4%)が福利厚生を重視するという結果が出ています。
ただし同調査では約46%の人が「社員旅行は不要」と回答しており、時代や価値観の変化により従来型の福利厚生が見直されていることも事実です。
しかし、「従業員エンゲージメントを高めた企業事例」で紹介したはとバス様では、自社の従業員の声に耳を傾けた結果、社員旅行を「希望制」「明確な目的設定」という工夫を加えて復活させ、異職種間交流によるエンゲージメント向上を実現しています。重要なのは、一般的なトレンドを参考にしつつも、最終的には自社の従業員ニーズに基づいた施策設計を行うこと。
適切な設計と運用を実践すれば、時代に合わないとされる施策を効果的に機能させられる可能性もあるのです。
エンゲージメントを上げる福利厚生の選び方
効果的な福利厚生を設計する際は、3つの軸で考えてみましょう。
- 公平性…雇用形態や職種による不合理な格差をなくし、基準を明確にした制度設計が重要です。
- 利用しやすさ…申請手続きを簡素化し、制度の存在と使い方を従業員にしっかりと伝えることがポイントになります。
- 多様性への対応…育児・介護・学習・健康など、さまざまなライフイベントに幅広く対応できるメニューを用意しましょう。
具体的な進め方として、まずはパルスサーベイや1on1で従業員の声を継続的に収集。数値と自由記述の両面からニーズを把握します。その上で、住宅・通勤手当のような生活直結型と研修・健康プログラムのような成長支援型をバランス良く組み合わせるようにしましょう。リモート環境が定着した現在では、オンラインで利用できるメニューの充実も欠かせません。
導入後は利用率・満足度・eNPS・離職率を定期的に測定し、データに基づいて継続的に改善していく必要があります。これらの客観指標を整備しておけば、労使双方が同じ事実に基づいて合意形成を進められるでしょう。
会員数日本一の福利厚生サービスで、従業員エンゲージメントを上げよう
多様なニーズに効率よく応えるなら、総合福利厚生サービスの活用が効果的。「ベネフィット・ステーション」では、育児・介護・健康・eラーニングといった生活・成長基盤からグルメ・レジャー・旅行まで、140万件以上のメニューを1人あたり月額1,000円(税別/10人以上の場合)からご提供しています。
従業員は自分に合う特典を自由に選べるため、物的エンゲージメントが底上げされるだけでなく、選択の幅があることで心的エンゲージメントも高まります。人事担当者にとっても、利用率や人気メニューランキングといった具体的なデータを把握して『直近12カ月の利用率○○%』といったように数字で示せるため、採用活動の現場で説得力あるアピール材料として活用できるでしょう。
離職率改善・人材獲得・労使交渉の材料づくりに、福利厚生を通じたエンゲージメント向上は欠かせません。ベネフィット・ステーションのサービス概要、導入事例や福利厚生に役立つ資料は下記から無料でダウンロードいただけます。福利厚生施策についてお悩みのことがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
ワークライフバランスの充実を支援する
福利厚生サービス ベネフィット・ステーション

待機児童問題/介護離職者の増加など、ワークライフバランスを取り巻く環境には問題が山積しています。
フレキシブルな勤務形態、休業・休暇制度を整えることは大前提として必要ですが、それだけでは育児・介護にかかわる金銭の問題や情報の提供不足といった課題が残ります。
福利厚生サービス ベネフィット・ステーションの導入により上記の課題を解決することができます。
①【育児】保育園探しのお手伝いや認可外保育施設利用時の割引等があり、保育と仕事の両立を支援できる。
②【介護】介護情報の無料提供・無料相談、介護用品購入費用の一部還付を受けられ、介護離職を防止する。
また、従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどありません。
ぜひ人事制度の改定と併せて福利厚生制度の拡充を検討していきましょう。