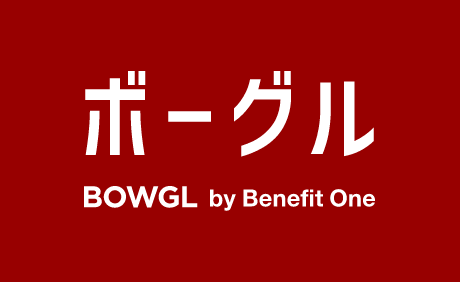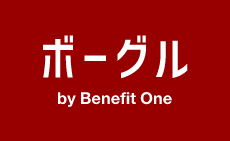男性が「育児休業」を取らない理由とは?育休取得率を上げるためのポイント

ワークライフバランス推進の取り組みが進むなか、企業にとって課題のひとつとなるのが「男性従業員の育児休業・休暇の取得」です。育休は男性にも当然に与えられた権利でありながら、厚生労働省の調査によると2020年度の日本の育児休業取得率は約12.65%と低調です。確かに、2019年度の7.48%からは飛躍した数値かとは思いますが、ユニセフが「先進国における家族にやさしい政策ランキング」という、先進国31カ国を対象に調査した育児休業給付金の支給対象となる男性の育児休業期間で日本は30週間で首位でした。
日本は育休を取得しやすい環境にもかかわらず、なぜ育児休業の取得率は低いのでしょうか。そして、この現状から育休を取得しやすい環境へと改善するために、企業側ではどのような対処をすべきなのでしょうか。今回は、男性従業員がなぜ育休を取らないのか、その理由と対応策について紹介します。
目次
人手不足でも労働生産性を向上させるには 人手不足の今、以下のような課題には早急に取り組む必要があります。 ・離職率の低下、採用力の強化 ベネフィット・ステーションは、従業員満足度を向上し、健康経営やスキルアップを促進する総合福利厚生サービスです。
・物価上昇に対抗できる経済支援
・従業員満足度の向上
・多様性のある働き方の選択肢の増加
・育児・介護と仕事の両立支援
グルメ・レジャー・ショッピング・スポーツ・旅だけでなくeラーニングなどの学習コンテンツ、育児・介護・健康・引っ越しなどライフイベントに関わるものまで、140万件と幅広いメニューを取りそろえています。
月額1人当たり1,000円~で上記課題の解決にオールインワンで寄与します。
資料は無料でダウンロードが可能です。
ぜひご覧ください。
男女が取得できる「育児休業制度」とは?

産前産後休業は女性のみに与えられる制度ですが、育児休業制度は男女問わず取得できる制度です。育児休業の基本と、男性の育児休業の特徴を紹介します。
育児休業制度とは
育児休業制度とは、育児のために休業したい従業員が生活の保障を受けながら休業できる制度です。育児・介護休業法によって定められているため、育児休業に関する制度がない企業の従業員も利用することができます。
休業中は雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。休業期間は原則として子どもの誕生から1歳までの間ですが、子どもを保育園に預けられないといった理由がある場合は1歳6ヶ月まで延長でき、その後も特別な事情がある場合は最長2歳まで再延長が可能です。また、「パパ・ママ育休プラス」という制度を利用すると、育休期間が1歳2ヶ月まで延長できるようになるなど、夫婦が協力して育児休業を取得できる仕組みも整備されています。
2022から2023年における法改正での変更点
2021年6月9日に育児・介護休業法が改正され、2022年4月1日に施行されました。
4月1日の施行内容は、育休を取得しやすい雇用環境の整備をすることや、妊娠・出産を申し出た場合に事業主である企業が個別に本制度を周知するとともに育休取得の意向確認が企業に義務付けられました。また、契約社員やアルバイトなど有期雇用労働者の育休取得においては、これまで1年以上雇用していることが条件でしたが、今回の法改正で雇用期間が廃止されました。
育児休業は原則、子ども一人に対して1回のみの取得となりますが、男性に限っては2回取得できる「パパ休暇」という制度がありますが、10月1日から子どもの出生後8週間以内に最長で4週間まで2回に分割取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設されるとともに、パパ休暇は廃止されます。また、育休制度自体も2回に分割して取得可能となりますが、取得の都度、申請が必要です。
そして、2023年4月1日からは育休の取得状況を公表するように義務化されます。
「育児休業」と「育児休暇」の違い
育休は「育児休業」と「育児休暇」の2つに大きくわけることができます。
「育児休業」とは、前述のとおり法律によって定められた休業制度のことで、一定の条件を満たせば国から育児休業給付金を受給することができます。
一方で、「育児休暇」は企業ごとに定める休暇制度です。企業が独自にガイドラインを定めて運用し、育児休業を取得できない人が利用したり、育児休業取得者が併用して利用したりします。優秀な人材を確保するために、法律で定められている基準を上回る育児休暇制度を整備する企業が増え、育児を取り巻く状況は変わりつつあります。
男性の育児休業取得率は40.50%
厚生労働省が2025年に発表した「令和6年度雇用均等基本調査」によると、2024年度の男性の育児休業取得率は40.5%で2023年度の30.1%に比べると大きく改善しました。しかし、女性の取得率86.6%と比べると、その取得率の低さは明らかです。厚生労働省は2020年までに男性の育児休業取得率を13%まで上げることを目標としていましたが、わずかに及びませんでした。また、2025年の育休取得率の目標は30%でしたが、この目標は2023年度の時点で達成されており、今後も男性の育休取得率は改善傾向が続くでしょう。
競合他社との差別化をはかる!企業のイメージアップは「ベネフィット・ステーション」で 人生100年時代と言われるようになり、定年年齢の引上げや定年廃止が進んでいます。 例えば「仕事とプライベートの充実ができる働きやすい会社か」「風通しが良い社風で一緒に働く人と一体感を持つことができる働きがいがある会社か」といった不安を払拭する必要があります。 これらの課題は、福利厚生サービスベネフィット・ステーションの導入で解決すること出来ます。 1. 140万件以上のサービスが利用できるため、年齢や性別関係なく、従業員の多様なニーズに応えることができる 2. 企業の福利厚生制度として「スポーツジム割引」「育児・介護補助」などの記載が出来るため、競合他社との差別化ができる 従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどありません。 ぜひ、企業のイメージアップや労働環境の改善策の一つとして、福利厚生制度の検討をしましょう。
少子高齢化による人手不足の原因の一つとなっている中で、「企業のイメージアップ」は離職率低下や若手の人材確保において重要な役割を担います。
男性の育児休業取得率が低いのはなぜ?

男性の育児休業取得率が低い背景には、どのような理由があるのでしょうか。この調査で厚生労働省が発表した「令和5年度労働者調査」を見てみましょう。男性が育児休業を取得しない主な理由は以下のとおりです。
業務が繁忙で職場の人手が不足していた:38.5%
職場が育児休業を取得しづらい雰囲気だった:33.7%
自分にしかできない仕事や担当している仕事があった:22.1%
収入を減らしたくなかった:16.0%
この調査で、男性が育児休業を取得しない主な理由として、人材不足や仕事の性質、会社の雰囲気を理由に休業申請ができないという人が多く、職場環境が大きく関係していることがわかります。
続いて、育児休業・休暇取得者の職場で実施されていた企業の取り組み(主に男性に対するもの)を確認しましょう。
育児休業給付金以外による所得の保障:45.5%
人事からの育児休業に関する周知:35.9%
上司や管理職による休業取得の呼びかけ:27.5%
育児休業取得者の職場では、育児休業を取得しない理由に挙がっていた「収入を減らしたくない」という課題に対して対策を講じて取得しやすい環境づくりに取り組んでいます。そして、人事や上司の働きかけによって職場環境の整備が進み、育休を取得しなかった人の職場より休業申請しやすい状況であることもうかがえます。
福利厚生だけじゃない!働き方改革を推進する「ベネフィット・ステーション 学トクプラン」 ベネフィット・ステーションは「福利厚生」「健康支援」「教育・研修」をワンストップで提供しています。 ・充実した育児、介護支援サービス その他、140万件以上のサービスが本パッケージに含まれています。 以下より無料で資料のダウンロードが可能です。
働き方改革への対応を一手にサポート致します!
・オンラインでの社員研修、eラーニングサービス
是非この機会にお試し下さい!
男性が育児休業を取得した場合の収入は?
前項で紹介した調査結果において、給与・賞与に代表される収入は気になる事項のひとつであることがわかりました。そこで、育児休業中に得られる収入についても触れておきましょう。
育児休業を取得した場合は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。金額はそれまで支給されていた給与の67%となりますが、育児休業給付金には所得税、社会保険料、雇用保険料がかからないため、休業前の手取り給与の約8割が支給されるイメージです。
支給額は休業開始ののち半年を過ぎると前賃金月額の50%に減りますが、パパ・ママ育休プラス制度を活用し、男性・女性それぞれが半年間ずつ育休を取得した場合は、1年間にわたって前賃金月額の67%が支給されます。育休中の収入に不安を感じる男性にとっては、安心できる制度といえるでしょう。
男性の育休取得のために企業が実施すべきこと

男性の育児休業取得率を向上させるためには、「職場環境の改善」「育休の周知」「制度の充実」の3つの観点から推進していくことが求められます。
職場環境の改善
前項の調査によると「休んだら周りに迷惑を掛けてしまう」「自分にしかできない仕事がある」という理由で育児休業・休暇を取得できない男性従業員が多いことがわかりました。そのため、まずは人員不足で従業員の負担が大きくなっていないか、業務が属人化していないかを確認しましょう。
人材不足という課題に対しては、業務フローの見直しや改善、ITツールの導入やDXによる自動化、テレワークを導入するなど業務効率化に着手します。また、変化が激しい世の中で働き方が多様化する現代は、フルタイム雇用でなくても優秀な人材を雇用できる場合がありますし、メンバーシップ雇用からジョブ型雇用へ切り替えることも方法の一つです。新しい人材の採用も視野に入れ、積極的に職場環境の是正に取り組みましょう。
業務が属人化している場合は、定期的にジョブローテーションを実施し、スキルやナレッジなどの情報や技術を共有できる仕組みを作ります。従業員が「自分も育児休業を取得できそうだ」と思える環境にしていくことがポイントです。
育休の周知
育休を取りやすい雰囲気づくりも重要です。まずは上司や管理職、次いで従業員全体への周知に取り組みます。女性の育休に関しては理解があっても男性の育休には抵抗があるケースは多いものです。管理職に対して社内研修をおこなうなど、徹底した意識改革が必要です。
家事と育児の両立を支援することが目的の「出生時両立支援助成金」は、男性が育児休業を取得しやすい職場環境づくりや必要な手続きをおこない、配偶者の出産後8週間以内に育児休業を連続5日以上取得させた企業に対して支給されるというものです。男性労働者の育休取得率を3年以内に30%以上向上した場合にもこの助成金は支給されます。
制度の充実
育児休業制度でカバーしきれない部分は、企業が独自で制定する育児休暇制度で対応しましょう。具体例として、育児休暇制度には子どもの行事に参加するときや看護したいときに取得できる「育児参加休暇」、配偶者の出産時に取得できる「配偶者出産休暇」などがあります。
しかし、このような新たな制度の策定が難しい場合は、福利厚生制度のアウトソーシングを活用する方法もあります。いずれにしても、企業は従業員に対して育児をサポートする姿勢を見せることが大切です。このような企業の取り組み事例は、厚生労働省の両立支援総合サイト「両立支援のひろば」や、イクメンプロジェクトのホームページでチェックできます。
総合福利厚生サービス ベネフィット・ステーション ベネフィット・ステーションは、従業員満足度を向上し、健康経営やスキルアップを促進する総合型福利厚生サービスです。 さらに ・お得な特典や割引がついたサービスを会員企業の従業員様が給与天引きでご利用頂ける、給与天引き決済サービス などをご用意しています。
グルメやレジャー、ショッピングだけでなくeラーニングや介護・引っ越しなどライフイベントに関わるものまで、幅広いメニューを取りそろえています。
・Netflixが見放題のプラン
育休の活用促進には人事の支援が不可欠
2025年の育休取得率の目標が50%ということと、働き方の多様化にともない男性の育休取得率は今後ますます向上すると予測されます。企業の将来を担う子育て世代が安心して働ける環境づくりは、あらゆる企業にとって向き合わなければならない要件のひとつといえるでしょう。特に、男性の育休に関する従業員の意識改革では、人事の働きかけが大きく左右します。従業員の立場に立って、将来を見据えた環境整備に取り組んでいきましょう。
ベネフィット・ワンの福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」では、育児に関する様々なメニューをご用意しています。その中でも「学トクプラン」では、育児に関するメニューはもちろん、ワークライフバランスの充実、健康経営の推進、教育・研修の支援をトータルでサポートする約140万件のサービスを地域・世代間格差なく平等にご利用いただけます。育休を含む福利厚生制度の環境整備の際に、ぜひご検討ください。
ワークライフバランスの充実を支援する
福利厚生サービス ベネフィット・ステーション

待機児童問題/介護離職者の増加など、ワークライフバランスを取り巻く環境には問題が山積しています。
フレキシブルな勤務形態、休業・休暇制度を整えることは大前提として必要ですが、それだけでは育児・介護にかかわる金銭の問題や情報の提供不足といった課題が残ります。
福利厚生サービス ベネフィット・ステーションの導入により上記の課題を解決することができます。
①【育児】保育園探しのお手伝いや認可外保育施設利用時の割引等があり、保育と仕事の両立を支援できる。
②【介護】介護情報の無料提供・無料相談、介護用品購入費用の一部還付を受けられ、介護離職を防止する。
また、従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどありません。
ぜひ人事制度の改定と併せて福利厚生制度の拡充を検討していきましょう。