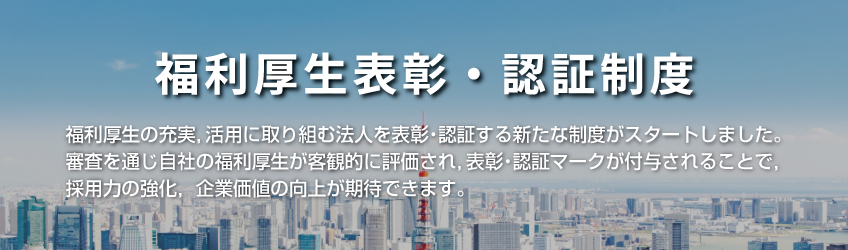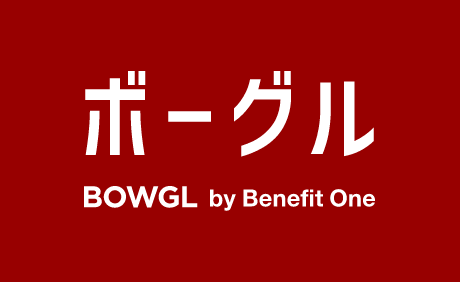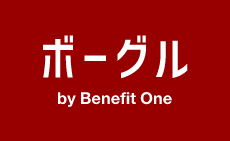【令和版】会社の福利厚生ガイド【事例アリ】

真似したい!福利厚生で注目される会社の事例集
「ハタラクエール」とは、株式会社労務研究所(ROUKEN)が年に1度開催している福利厚生表彰・認証制度です。エントリーした法人(企業・団体・自治体)から得たアンケートやヒアリングをもとに、4名の学識者で構成された審査委員会が以下の6項目ついて審査を行います。
- 1.経営課題への対応
- 2.現状把握
- 3.制度の充実度
- 4.運用状況
- 5.福利厚生への熱意
- 6.その他
選定基準で高評価を獲得した法人は「福利厚生推進法人」として認証され、その中から特に優れた法人が「優良福利厚生法人」として選出されます。
「福利厚生推進法人」または「優良福利厚生法人」と認定された法人は受賞の周知や付与されたロゴマークの使用が可能となり、時代に即し、従業員満足度も高く会社の利益向上にも間接的に寄与する福利厚生を展開している企業であるというブランディングに活用できます。売り手市場の中、福利厚生に取り組む優良企業との専門機関からの客観的な評価は、企業にとって強力なアピール材料となるでしょう。
ここでは、ハタラクエール受賞企業の中から福利厚生の見直しや拡充の参考となる事例を紹介します。
事例1. アコム株式会社~1万件もの社員の声を福利厚生に活かす会社
東京都千代田区に本社を置くアコム株式会社は、ローンやクレジットカード事業を展開する会社です。同社は、2022年から2025年まで4年連続でハタラクエールの「優良福祉厚生法人(総合)」を受賞しました。総合的に高スコアを獲得し、2022年度のハタラクエールでは、特に非正規従業員を含めた福利厚生の充実さにおいて高く評価されました。
もともと従業員を大切にする風土を持つ同社。しかし、業況が悪化した2006年には、福利厚生の一部制度を廃止または縮小せざるを得ない状況に追い込まれたそうです。その後業況は回復の兆しを見せ、「厳しい状況の中でも辞めずについてきてくれた従業員に報いたい」との想いが現在の制度を確立するきっかけとなりました。
同社の福利厚生に携わっているのは、企画チームと厚生チームです。企画チームは福利厚生に関する課題を見つけ、制度の見直しや新制度の設置などを検討・決定します。厚生チームは、企画チームと情報を共有し、制度のルールなどを取り決めて運営を行います。
同社は年に2度従業員意識調査を実施し、現場で働く従業員たちの声を集めています。寄せられるコメントは1万件を超しますが、人事担当者は全てのコメントに目を通すといいます。また、従業員で構成されているES(従業員満足)ワーキンググループも情報収集において不可欠な存在。ESグループは全国の営業所を回って従業員から直接話を聞き、職場の現場や社員の要望などを把握して福利厚生チームと情報を共有しているそうです。
1時間単位で休みを取得できる「時間単位年休」は、育児や介護などの理由から「柔軟に休みたい」という従業員の声を反映させてできた制度の一つ。導入してからライフ・ワーク・バランスが取りやすくなったと好評です。
幅広い分野において複数の福利厚生を展開している同社が、安定した福利厚生の運営と全従業員が利用しやすい環境整備を目指して導入したのが福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」でした。導入後の活用率を上げるため、非正社員を含む全従業員にレジャーやグルメ、健康などさまざまな分野で利用できるポイントを付与するカフェテリアプランを取り入れているため、 ポイントを通じて家族間や従業員間でコミュニケーションを取りやすくなり、さらに同社の評判は従業員の家族にも広がったといいます。
さらに浸透率を高めるため、本社メールを活用して福利厚生に関する情報を全従業員に配信した結果、ベネフィット・ステーションの利用率は99%に達したそうです。
真似できるPOINT
- 福利厚生業務を遂行する専門チームを設置する
- 現場の声を集約し、新たに導入する制度の参考にする
- 自社で完結するのが難しい場合は、アウトソーシングサービスの利用を検討する
事例2. コネクシオ株式会社~利用率99%を誇る、福利厚生活用度の高い会社
コネクシオ株式会社は、伊藤忠商事株式会社を親に持ち、携帯電話の卸売事業などを展開している会社です。同社は2020年から2022年まで連続でハタラクエールの「優良福利厚生法人」に選出され、2023年・2025年は「推進法人」に選出されました。
「人をつなぐ、価値をつなぐ」を理念に掲げている同社。福利厚生では、全従業員が公平に利益を得られる点にウエイトを置いて制度を企画・設計しています。
具体的には、復職支援や単身赴任者が帰宅する際にかかる交通費の補助、禁煙サポートプログラムの実施、育児や病気で休職している従業員に対する復職支援など、個人の事情に合わせた制度を構築しました。さらに、従業員に働きがいを感じてもらいたいとの想いから、教育プログラム「コネクシオカレッジ」の設立や女性活躍推進を展開しています。
制度の内容は、従業員のニーズに合わせて改善することもあります。その一例として挙げられるのが保育料の補助です。育児・仕事両立補助の一環として同制度が誕生した当初は「保育料の半額補助」がルールでしたが、従業員から要望が多数寄せられ「1か月3万円の上限を設けた全額補助」へ修正したといいます。
同社ではベネフィット・ステーションのカフェテリアプランを導入し、幅広い福利厚生を提供しています。ポイントや全社メールを使って制度の活用を促した結果、ベネフィット・ステーションの利用率は99%まで伸びました。現在特に力を入れているのは、従業員の健康増進なのだとか。ウォーキング施策などの各種健康施策を実施し、回を重ねるごとに参加する従業員の数が増えているそうです。
真似できるPOINT
- 現在提供している制度を見直し、従業員のニーズに合わせて改善する
- 例えば「従業員の健康増進」など福利厚生で実現したいテーマを一つに絞り、関連した制度の導入を検討
- 既存の福利厚生サービスを活用して展開する
事例3. ドリームビジョン株式会社~福利厚生の充実で離職率を1/3に下げた会社
東京を拠点にシステム開発事業を展開するドリームビジョン株式会社は、ハタラクエール2022において「優良福利厚生法人(福利厚生への熱意部門)」に選ばれました。「⑤福利厚生への熱意」が高く評価されたのが主な受賞理由です。また、2023年・2024年・2025年と連続で「推進法人」にも選出されています。
離職率の高さに悩まされた経験から、「日本一エンジニアを大切にする会社」とのコーポレートビジョンを掲げるようになった同社。目的をかなえる手段として選んだのが、福利厚生の拡充でした。
同社はHRM事業部を立ち上げ、人事に関する業務と従業員のフォローアップを専門に行っています。同社が提供している福利厚生は、従業員が日ごろ利用しているサービスをお得に利用できるものが多い点に特徴があります。
例えば「書籍購入補助制度」は、仕事に関連した専門書籍の購入代を2か月6,000円まで負担するという福利厚生。人気の高い「昼食チケット」は、毎月利用できる6,500円分の「昼食チケット」のうち会社が約半額を補助するというものです。
同社の福利厚生拡充の成果は、離職率の大幅な低減に現れました。2013年では26.32%だった離職率が、2021年には7.81%に低下したというのですから驚きです。
真似できるPOINT
- 非課税枠を利用するなど従業員に負担のかからない制度を採用する
- 従業員が仕事中に利用するサービスなどを調べ、お得感のある福利厚生を提供する
事例4. サントリーホールディングス株式会社~福利厚生×ボランティアで参加率を4倍にした会社
アルコールや清涼飲料水の製造・販売大手のサントリーホールディングス株式会社は、ハタラクエール2020の「優良福利厚生法人(総合)」に輝きました。”Suntry People Way”を掲げている同社は従業員一人ひとりの幸せと健康を願い、子育て支援や住宅支援など従業員のライフスタイルを考慮したさまざまな福利厚生を展開しています。また、多様化する従業員のニーズに対応するため、「高齢者」「女性従業員」「外国人労働者」「LGBT」「障がい者」別にサポート体制を整えている点も特徴的です。
同社は「インセンティブポイント制度」を導入し、従業員のボランティア活動の活性化に取り組んでいます。ボランティアと福利厚生を組み合わせるきっかけとなったのが、同社が実施した従業員の意識調査でした。同調査によって、ボランティアに興味を持っているものの最初の一歩を踏み出せない従業員が多いことが分かったのです。
そこで人事部が中心となり、ボランディア強化月間を実施します。ボランティアに参加した従業員に対してインセンティブポイントの付与を始めてからは、ボランティア活動への参加者数が通常の4倍に増えたといいます。
真似できるPOINT
- 福利厚生にボランティアなどの社会貢献活動をプラスする
- 従業員の参加を促すためにポイント制度を活用する
事例5. HITOWAケアサービス株式会社~低かった福利厚生への満足度を急上昇させた会社
HITOWAケアサービス株式会社は、デイサービスなど生活総合支援サービス業を全国展開している会社。これまでハタラクエールの「福利厚生推進法人」を2度受賞しています。
同社が福利厚生に本格的に取り組み始めたのは2018年からです。約3,000名の従業員に対して行った意識調査で、福利厚生に対する満足度が低いという結果が出たのがきっかけでした。また、同調査では、職員同士でコミュニケーションが取りづらい現状も浮き彫りとなりました。
同社は満足のいく福利厚生を従業員に提供するために、ベネフィット・ステーションを導入しました。ショッピングやレジャー、グルメ、旅行、健康支援など多岐に渡る福利厚生を提供できるようになったうえ、eラーニングの活用によって社内研修制度の充実にもつながりました。従業員と家族が一緒に利用できるサービスも含まれているため、従業員のプライベートにおける満足度の向上にも寄与しているといいます。
同社はベネフィット・ステーションとともにインセンティブポイントも導入し、「サンクスポイント機能」を利用して貯まったポイントを従業員間で贈り合ったりポイントの使い道で話が盛り上がったりするなど、独自のコミュニケーション文化が育ちつつあります。
幅広い年齢層の従業員を抱える同社では、イリーゼアプリ(同社アプリ)と施設内に設置できる周知媒体を使って制度を効率良く周知しているとのことです。
真似できるPOINT
- 解消したい課題を一つに絞り、福利厚生で解決できないかどうかを検討する
- 「従業員が何に不満を持っているのか」を見つけ、それを解消できる福利厚生を提供する
事例で紹介した企業は福利厚生の重要さに気づき、地道に努力を重ねて制度を拡充した結果、従業員の満足度の引き上げに成功しています。展開している福利厚生の種類は各企業で異なるものの、共通しているのがベネフィット・ステーションの導入でした。
「ベネフィット・ステーション」は、弊社ベネフィット・ワンが提供している総合福利厚生サービス。学習や育児、住宅、レジャーなどさまざまな分野が優待価格となるなど、利用できるサービスは140万件以上となっています。 また、多様化する企業のニーズに合わせて業務代行やポイント制度などのサービスもご用意しています。
従業員の満足度を高めやすいサービスがすでに用意されている点、複数の福利厚生を運営しやすい点から、福利厚生に関する多岐に渡るニーズに効率的・効果的に応える手段として多くの企業がベネフィット・ステーションを導入・活用されています。
「大手がやっている福利厚生なんて、中小の会社には真似できないよ…」とお思いの方もおられるかもしれませんが、ベネフィット・ステーションは会社の規模を問わず約16,000団体が導入し、会員数は約1,220万人を超えています(2025年4月時点、福利厚生、CRMおよびパーソナルの合計会員数)。従業員1名1ヶ月あたり1,000円~というコストパフォーマンスの良さも、多くの企業に導入いただいている理由のひとつです。
「会社の福利厚生への満足度が低い」「従業員のニーズがバラバラで、何から改善したらよいのか分からない」そんな会社の福利厚生をスムーズに拡充する手段として、ベネフィット・ステーションの活用を検討されてみてはいかがでしょうか。
|
★社員1名月1,000円~で福利厚生を拡充! |
会社が目指すべき福利厚生の在り方とは
改めて知っておきたい「福利厚生とは」
福利厚生とは、企業が自社の従業員(家族を含む場合もある)に対して提供する報酬(賃金は除く)の総称です。「福利」とは人の幸福や利益のことで、「厚生」は健やかで安心できる生活を意味します。有給休暇や雇用保険に代表されるように、従業員が安心して仕事に励み自身の生活を豊かにするのを支えることが福利厚生の目的です。
福利厚生の種類
法定福利厚生
法律で定められている福利厚生を法定福利厚生といいます。要件から内容まで法律で細かく規定されており、企業は法律に従って実施します。
法定福利厚生は企業が負う義務であり、全く提供していない場合は法律違反とみなされます。
<法定福利厚生の種類と概要>
- 健康保険:従業員またはその家族の病気や死、出産などに対して手当金を支給する医療制度
- 厚生年金保険:主に老後資金の蓄えを目的とした年金制度
- 雇用保険:失業または休職時に生活をサポートするために手当金を支給する保険制度
- 労災保険:従業員が勤務中(通勤も含む)に病気やケガをした場合に、医療費などをカバーする保険制度
- 介護保険:介護が必要になった際に介護費を一部負担する保険制度
- 子ども・子育て拠出金:児童手当など、育児費用の軽減を目的とする拠出金
法定外福利厚生
法定福利厚生以外の福利厚生を法定外福利厚生といいます。企業が自由に制度の要件や内容を決められますが、福利厚生の導入や運営する際に発生したコストを福利厚生費として認めてもらうには、以下の要件を満たすことが必要です。
- 全従業員を対象としている
- 支出する金額が福利厚生として妥当な範囲である
- 賃金に該当しない
法定外福利厚生は、以下のように分野別に分類される傾向にあります。
<法定外福利厚生の種類と福利厚生の例>
- 住宅に関するもの:住宅手当、家賃補助
- 通勤に関するもの:通勤手当
- 食事に関するもの:食費補助、弁当支給、社員食堂
- 子育ておよび介護に関するもの:保育料補助、短期間勤務制度、介護費用の補助
- 慶弔および災害に関するもの:結婚祝い金、災害見舞金、慶弔休暇
- 健康に関するもの:人間ドック費用の補助、フィットネスジム利用料金の一部負担
- 働き方(ライフ・ワーク・バランス)に関するもの:リフレッシュ休暇、在宅勤務
- 自己啓発に関するもの:資格取得や専門書籍購入補助、 セミナー受講などにかかる費用の補助
- 余暇に関するもの:レジャー施設や宿泊施設の利用料金の補助
- 財産形成に関するもの:企業型DC(企業型確定拠出年金)
福利厚生を拡充するメリット
従業員の満足度を向上させる
福利厚生がもたらす最大のメリットは、従業員の満足度の向上です。
ライフ・ワーク・バランスが整うと、従業員は過度に会社に拘束されることなく空いた時間を自由時間に充てられるため、プライベートでの充実感を得やすくなります。また、住宅手当などの金銭的なサポートも、満足度をダイレクトに押し上げます。家族も利用できるクーポンや施設利用の割引券の付与も、従業員の満足度アップにつながるでしょう。
離職率の低下や従業員の定着率向上につながる
従業員の満足度向上は、さらなるメリットを企業にもたらします。期待できる効果の一つとして、離職率の低下が挙げられます。
昔よりも転職が当たり前の時代になりましたが、他社と比べて働きやすい環境が整っていれば、従業員は労力を使ってまで転職しようとは考えなくなるでしょう。従業員が「働き続けたい」と考えれば、定着率も自然に上がっていきます。
離職率の低さと定着率の高さは求人の際には「長く働けそうな会社」との印象を与えやすくなるため、採用コストの削減に寄与します。
企業の発展が見込める
満足度の高い従業員は主体的に働く傾向にあり、結果として労働生産性が上がります。労働力の高い従業員が増えれば増えるほど労働生産性はアップして企業全体の生産性の向上につながるため、組織の成長と発展の下支えとなるでしょう。
福利厚生拡充のデメリット
コスト面で負担がかかる
例えば新たに制度を導入する場合、システムの導入や構築といった初期費用、制度を運営するための毎月の費用が発生します。制度の対象となる従業員の数が多くなればなるほどコストはかさむでしょう。潤沢な予算があれば別ですが、利用したい制度があってもコストがネックとなれば全てを導入することが困難になります。
従業員に負担がかかる
従業員に関する情報収集や利用状況の管理、従業員の意識調査など、福利厚生の運営は細かな作業の連続です。決して片手間でできることではなく、福利厚生業務を専門にする担当者や専門チームが必要となるでしょう。
担当者がすぐに見つかれば別ですが、新たに人を採用する場合は、採用が決定するまでに費用や時間を要します。企業によっては、「福利厚生を充実させたいが、リソースが不足している」との理由で断念せざるを得ないかもしれません。
平均的な福利厚生費
日本経済団体連合会が2019年に発表した資料によれば、従業員1人にかかる1ヶ月の福利厚生費は平均108,517円でした。
これは、従業員に支払われる現金給与総額(給与や賞与を含む)の19.8%に相当する金額。従業員の賃金の約2割が福利厚生費としてかかる計算です。あくまでも平均金額ですが、福利厚生費を検討する際のおおよその目安となるでしょう。
※参照:【PDF】日本経済団体連合会「第64回福利厚生調査結果報告」(2019年度)
https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/129_honbun.pdf
ほかの会社はどうしてる?福利厚生の傾向
福利厚生への関心が高まる中、企業はどのように対応しているのでしょうか。独立行政法人 労働政策研究・研修機構が公開している資料をもとに、昨今の企業動向を紹介します。
企業が福利厚生の拡充に動くのは、人材確保や定着が主な動機です。多くの企業は、従業員の満足度を高めることが人手不足の問題を解消する手段と考えているのです。
福利厚生における従業員の支援にはトレンドがあり、現在のトレンドは「ライフワーク支援」「ヘルスケア支援」「ライフプラン支援」の3つです。最近では働き方改革を目的に福利厚生を活用する動きも活発化しています。正社員化する代わりに福利厚生を充実させて非正規従業員 の待遇改善を図るといった施策がその一例です。
企業がトレンドに合わせて福利厚生を設計・導入する動きが高まるとともに、福利厚生サービスは多様化しています。企業は複数の福利厚生を提供する傾向にあり、その運営を外部の業者に委託する企業も増えてきました。福利厚生サービスの運営を受託する大手5社の受託状況を見ると、2005年は11,600件でしたが、2017年には20,000万件を突破しています。
※参照:【PDF】独立行政法人 労働政策研究・研修機構「企業における福利厚生施策の実態に関する調査」(2019年)
https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2018/08_09/016-021.pdf
令和の福利厚生トレンドとは?
令和の時代において特筆すべきは、コロナウイルス感染症の流行によって働き方が大きく変化した点でしょう。インターネットを利用したリモートワークが活発化し、テレワークを活用する人も増えました。 働き方の変化に伴い、福利厚生に対する労働者の意識にも変化がありました。
厚生労働省が発表した『令和5年版厚生労働白書』によれば、テレワーク経験者は就業者全体と比べて働き方(特に柔軟な働き方)に対してより高い関心を持っていることが分かりました。さらに、テレワーク経験者全体のうちおよそ2割が充実した福利厚生に興味を示しているといいます。この数字は就業者全体の割合を上回っており、柔軟な働き方を選ぶ人は多彩な福利厚生を望む傾向にあるといえるでしょう。
若者の会社選びに対する意識も変化しています。『令和2年版厚生労働白書』では、休暇や補助金に関連した制度に必要性を感じている労働者の多さが浮き彫りとなりました。年代別で見ると、20~30歳代は40歳代以上よりも労働時間内で働ける点・柔軟な働き方が可能な点・福利厚生が充実している点を働くうえで重要視する傾向にあります。
転職サービスを提供するdodaが実施した調査を見ると、20~30代で満足度の高い福利厚生は、1位「慶弔・災害見舞金」2位「育児・介護制度」3位「出産お祝い金」でした。
急な出費や高額費用に対する補助は「従業員のことを考えている優しい会社だ」「お金の補助はありがたい」といった気持ちを引き出しやすく、満足度が高くなるようです。また、育児・介護休暇は会社を離れずに安心して育児や介護に専念できる安心感を従業員に与えます。
ハタラクエール受賞企業の多くが導入していた「カフェテリアプラン」も、満足度の高い福利厚生としてランクインしています。金銭的な福利厚生の拡充が難しい場合、安価で始められるベネフィット・ステーションのような福利厚生サービスを導入し、効率的に従業員満足度を上げる施策も検討してみる価値があるといえるでしょう。
※参照:【PDF】厚生労働省「令和5年版厚生労働白書」(21ページ参照)
https://h-crisis.niph.go.jp/wp-content/uploads/2023/08/zentai.pdf
※参照:【PDF】厚生労働省:「令和2年版厚生労働白書」(49ページ参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/000735866.pdf
※参照:DODA「【20代・30代実態調査】満足度の高い福利厚生制度は?」
https://www.dodadsj.com/content/200323_benefits-research/
幅広い種類の福利厚生を拡充できる
福利厚生サービス ベネフィット・ステーション

従業員満足度を高めるためには、福利厚生を幅広く用意する必要があります。
とはいえ、福利厚生を1から自前で整えるのは大きな労力がかかります。
そんなときに活用したいのが福利厚生サービスです。
ベネフィット・ステーションではレジャー・食事・育児・介護・財産形成といった幅広い福利厚生を一気に拡充することができます。
また、ベネフィット・ステーションは、
・一業者との契約で140万件以上のサービスが使えるようになる
・会員数は業界最大規模の1,220万人(※)が導入済
・導入企業法人数約18,100団体
(※2025年4月時点 ※福利厚生、CRMおよびパーソナルの合計会員数)
従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどないのも特徴です。
ぜひこの機会に福利厚生制度の拡充を検討していきましょう。