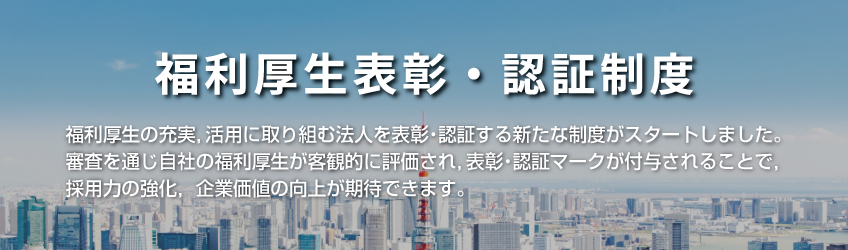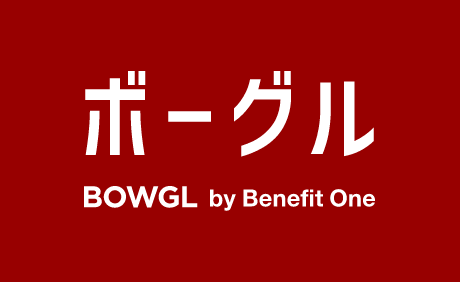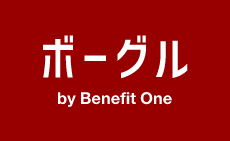【7分で分かる】ベースアップの考え方とは?【専門家がレクチャー】
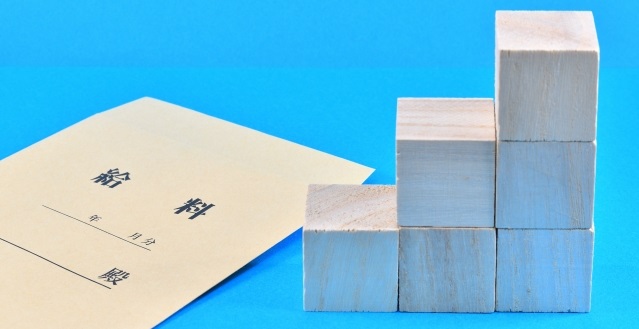
目次
【専門家が教える】ベースアップの考え方
産業革命を契機として、工場で働く労働者に家庭のようなサービスを提供することから始まった福利厚生制度。法で定められた福利厚生の他に、住宅手当や通勤手当など企業が独自に定める福利厚生についても当たり前のサービスとなりつつあります。
多くの企業が福利厚生を充実させていく中、人材を確保する効果的な手段として社員の待遇改善や福利厚生を戦略的に活用することを提案されている西久保浩二氏にお話を伺いました。
 |
プロフィール 西久保 浩二(にしくぼ こうじ)氏 1958年大阪府生まれ。神戸大学卒業後に大手生命保険会社での勤務を経て生命保険文化センター主席研究員を務める傍ら、筑波大学大学院修士・博士課程 を修了。博士課程単位取得後には東京大学客員准教授などを経て2007年山梨大学教授就任、2024年名誉教授。現在は福利厚生戦略研究所代表、政策研究大学院大学客員研究員、日本大学商学部研究員を兼務。 「国家公務員の福利厚生のあり方に関する研究会(総務省)」座長、「福利厚生表彰・認証制度」審査委員長など多数の公職・関連部会委員を歴任。『戦略的福利厚生の進化』 、『わが国の福利厚生の導入と利用の実態とその諸要因、そして有効性の検証』などの著書がある。 |
【考え方その壱】企業がベースアップを行うメリットとは?
インタビュアー(以下「イ」):労働基本法に規定されているように、労働者が不利益をこうむるような変更は困難なため、賃金テーブルを上げるベースアップは慎重に考えなければならないと思うのですが、それでもベースアップを行ったほうがよい場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
西久保浩二氏(以下、西久保氏):ベースアップのメリットを考える前に、そもそもベースアップをする必要があるのかという点は慎重に検討したいですね。
給与を上げる方法としては、ベースアップの他に定期昇給(定昇)があります。定期昇給は昇給の基になる賃金テーブルを一つ上に移動させることですが、ベースアップはその賃金テーブルに書いてある金額自体を上げるということ。1年間頑張ってくれたから一つ上の金額にしましょうではなく、基準を満たしておらずとも金額が上がるので、社員全体の賃金が増えるのです。つまりは実質賃金が上がるということなので、物価高対策になるのはベースアップの最大のメリットといえます。
イ:均等に従業員全体の賃金が上がるというのは安心ですね。
西久保氏:従業員に対してはもちろんですが、労働市場にも良い印象を与えることができます。ベースアップをすることで、「業績が好調である」「社員の生活のことを考えている」「賃上げに前向きな企業である」というプラスのメッセージを発信することができるのです。
賃金テーブルが上がるというのは初任給が高くなることでもあるのですが、同じような業種で給料に差があったら高い方に行きたくなる人が多いのは当然です。そういう意味では、採用力を高めて優秀な人材を集めることができ、離職を抑制できるというのもベースアップのメリットになります。
さらに大きな視点で捉えれば、ベースアップすることで従業員の消費を促し、景気を引き上げる効果があるという点もメリットです。
【考え方その弐】ベースアップする際の注意点とは?
イ:メリットを理解した上でベースアップの実施を検討しようとなった場合、企業が注意しなければいけないポイントはどのようなものがあるのでしょうか。
西久保氏:メリットがあるとはいえ、ベースアップは企業にとっての負担増であることには変わりありません。本当にベースアップをしなければいけないのか、他に従業員の生活を支援する方法はないのか、定期昇給では物価高に対応できないのか、労使交渉をする上でよく話し合う必要があります。
一度ベースアップをしてしまうと、賃料を下げることがなかなかできなくなります。これを「下方硬直性がある」と言うんですが、平成20年3月に施行された労働契約法に「不利益変更」という項目があり、労働者の同意を得ずに労働者に不利益な条件に変更することはできません。景気は浮き沈みがあるので、長い目で見るとベースアップにより人件費が増えれば経営を圧迫する可能性があるという点は無視できません。
先ほどメリットの中で労働市場に良いメッセージを発信できると言いましたが、遅からず同業他社もベースアップしてくることは容易に想像できますので、無理をしてベースアップをして一時期は他社よりも有利になったとしても、追いつかれて体力勝負となったときに負担だけが重くのしかかることになってしまうのです。
イ:逆に、他社よりも賃金水準が低い場合はやはりベースアップしたほうがよいのでしょうか
西久保氏:地域の同業種の企業よりも賃金水準が見劣りしているのであれば、思い切ってベースアップするのもひとつの手ですね。ただし、予算に余裕があればという条件はつきます。
逆に、すでに地域で賃金水準がトップクラスだった場合、ベースアップをする必要はないのではないでしょうか。従業員や入社希望者から「他社はベースアップしている」と言われても、「賃上げしなくとも給料はこちらのほうが高い」としっかり説明すれば理解は得られるはずです。比べるのはあくまで地域のライバル企業。大企業と比べても意味はありません。
繰り返しになりますが、ベースアップは最後の手段です。従業員の要求や社会情勢をよく見て、今、本当に求められているのはベースアップなのかどうかを見極める必要がありますね。
大事なのは、労使交渉が円満に帰結するということ。今は物価高なのでベースアップを要求されますが、仮に景気が悪くなり世の中でリストラの話が多く出てくれば、雇用を保障することが従業員にとっての最重要項目になることだってありえるわけです。
今、従業員にとって何が必要なのか。企業側が従業員の声をよくヒアリングし、要求に対してどのようにすれば満足度が上がるのか、その最善の手段とはベースアップなのかを吟味することが、企業と労働者が共生していくうえで非常に大切だと思います。
【注目】ベースアップではなく福利厚生を拡充するという考え方
ベアより福利厚生がおすすめな理由
単に給与を上げるだけでなく、福利厚生を充実させて社員の満足度を向上させることも賃上げ対策に繋がります。
ベア(ベースアップ)よりも福利厚生をおすすめする理由は3つあります。
1. 税制上の優位性
福利厚生は、条件を満たせば現金で支給することになる給与とは異なる税制上の取り扱いを受けるため、企業にとっても社員にとっても金銭的に有利になります。
企業の視点で見ると、借り上げ社宅費用や通勤手当、人間ドックの受診料などを損金として法人税法上の所得税の計算から控除することが可能です。社員の視点で見れば、ベア額によっては差し引かれる社会保険料や所得税、住民税などを鑑みると可処分所得はベア前と変わらない…という状態になる可能性があるため、給与として現金で支給されるのと同等のサービスを福利厚生として提供してもらえれば、ベースアップよりもお得になる可能性があるのです。
2. 社員の帰属意識と信頼度の向上
社員のニーズにマッチした福利厚生は、社員の会社に対する帰属意識や忠誠心を高める効果があります。
特に、出産や子育て、介護など社員がプライベートで負担が増えるライフステージに合わせた福利厚生サービスは、企業の「社員の生活を支えたい」というメッセージを伝えることにつながり、信頼関係の構築、離職率の低下につながります。
3. 個別ニーズへの対応
現代は多様性の時代。多角化する従業員のニーズに応えるためには、画一的なアプローチでは不十分です。同じ給与額でも、年齢や家族構成、ライフステージや価値観などによって必要な支援や福利厚生は異なります。社員に合わせて必要な支援や制度を拡充すれば、一律に賃上げ(ベア)するよりも社員の満足度を向上させることができるのです。
幅広くニーズに対応するには、カフェテリアプラン(選択型福利厚生制度)のような柔軟な制度を検討することも必要。社員が「自分にとって最も必要なサービスはどれか」を選択する権利を提供すれば、自分で選ぶゆえに満足感が高くなる傾向があります。
ベア回避にも有効な福利厚生事例
18万人が利用【日本電信電話株式会社(NTTグループ)様】
NTTグループでは、ベネフィット・ステーションで提供しているフィットネスクラブやレジャー施設の割引サービスにNTTオリジナルのサービスを加えて、正社員・非正規社員の分け隔てなくサービスを利用できるようにカスタマイズした結果、多くの社員が利用するようになったとのことで、 フィットネスクラブを1回500円で利用できるサービスが特に人気があるようです。
「社員が心身ともに健康に働ける環境を整えることで経営が安定する」という考えのもと、健診の機会を設けるだけではなく運動習慣の改善や栄養バランスの摂れた食事をするよう啓蒙するなど、社員の健康管理にも注力されているそうです。
非正規社員にも拡充【株式会社ベルシステム21様】
多数のコンタクトセンターを運営する株式会社ベルシステム21様は、その業種柄、契約社員が多いのが特徴。正社員を対象にベネフィット・ステーションを導入したところ利用率が高かったため、契約社員にも提供を開始されました。
利用者が増えれば運営コストも増えるものの、従業員の満足度が上がれば業績向上が見込め、離職率を抑えられれば採用コストが下がるという2つのメリットが上回ると感じておられるそうです。
利用率が99%超え【アコム株式会社様】
「はじめてのアコム」のキャッチフレーズで有名なアコム株式会社様は、2013年からご利用いただいているベネフィット・ステーションに加えて、全社員がより使いたくなるサービスとしてカフェテリアプランを導入されました。
カフェテリアプランとは、企業が設定した福利厚生サービスの中から社員が自分に必要なサービスを自分で選択できる制度のこと。このプランを導入するだけでなく利用率を上げるために、アコム様では全社メールを利用して社員へ周知し、サービスの利用を促してきました。それに反応していち早く利用した社員が起点となり、「もう使った?」「どのサービスがおすすめ?」と情報交換をしているようで、結果的にサービスが広まったと感じておられるとのことです。今では社員の利用率は99%、ポイントの消化率も80%を大きく上回っており、満足度の高さが伺えます。
社員ニーズを反映【プリマハム株式会社様】
加工食品の製造販売を行っているプリマハム株式会社様では、ニーズに合わせて自由にサービスを選べるよう、ベネフィット・ステーション及びカフェテリアプランを採用してくださっています。
導入するだけではなく、社員のニーズに合わせて選択できるメニューのカスタマイズを実施。導入初年度の2015年度には利用率が70%未満だったところ、2020年度には92.7%まで上昇しています。
インセンティブ・ポイント付与【大成温調株式会社様】
全国に拠点を構える大成温調株式会社様では、勤務エリアによって社員が享受できる福利厚生に差が生じないよう日々施策を練っています。その中で辿りついたのが、オンラインで利用できる「ベネフィット・ステーション」。グルメ・レジャー・ショッピングなどを優待価格で利用できる総合福利厚生サービスです。
加えて、ポイントを貯めることで欲しい商品と交換できるインセンティブ・ポイントシステムも導入。ウォーキングキャンペーンや誕生日ポイント、社員間でメッセージを交換すると貯まる「サンクスポイント」などを通じて、社員の満足度とコミュニケーションの向上を図っています。ポイントを貯めて商品と交換できれば支出が減るため、給与の上げ幅が小さくとも社員の満足度を上げることができるのです。
営業の稼働率が2倍に【損保ジャパンパートナーズ株式会社様】
保険代理店として全国に100箇所以上の拠点を持つ損保ジャパンパートナーズ様は、成績が優秀な社員の表彰制度を実施されていました。しかし、表彰される社員は約10人に1人。他の社員の頑張りに対しても還元したいと導入したのが「インセンティブ・ポイント」でした。
インセンティブ・ポイントは、成約した件数や本人が設定した目標を達成した場合にポイントを付与して、貯まったポイントで好きな商品と交換できる仕組みです。会社が成績上位者以外もきちんと評価していることを実感でき、自分へのご褒美やご家族へのプレゼントなどに活用できるため、社員のモチベーションアップにつながっているといいます。
ベネフィット・ステーションの導入企業は約16,000団体、会員数は約1,220万人(2025年4月時点、福利厚生、CRMおよびパーソナルの合計会員数)。グルメ・レジャー・ショッピングといったベースアップの代替策となりうる優待価格サービスに加えて、育児・介護、引っ越し等のライフイベントに関わる支援、さらにはeラーニングによる従業員のスキルアップまで、140万件以上のサービスから従業員がニーズに合ったものを選択して利用できます。
ベースアップが本当に得策かどうかは慎重に検討するべき。福利厚生によって従業員満足度を向上させるという選択肢も、一度検討してみてはいかがでしょうか。
|
★社員1名月1,000円~のベースアップ対策! |
ベースアップを考える前に知っておくべき基礎知識
そもそも、ベースアップとは?基本的な考え方
ベースアップ(略して「ベア」)とは、社員全体の基本給(ベース)の水準を引き上げる制度です。企業が物価上昇や業績向上などを理由として賃金テーブル(社員の給与基準を決める表)を改定することで、社員全員の基本給がアップします。
定期昇給との違い
定期昇給が「年功序列や前年の貢献度に応じた個人の昇給」であるのに対し、ベースアップは「全社的な給与水準の底上げ」という点で異なります。
<ベースアップ>
- 企業全体の賃金水準を底上げする措置
- 社員全員に適用される(個々の社員の年齢や貢献度とは関係なく決定される)
- 物価上昇や企業業績などの要因で実施される
- 毎年自動的に行われるものではなく、ある時期に経済状況や労使交渉により決定
<定期昇給>
- 個人の年齢や勤続年数に基づく昇給
- 毎年一定時期に自動的に行われる
- 個人の成長や経験の蓄積に対する評価(仕事に反映されるという前提)
- 賃金カーブに沿って上昇する仕組み
賃上げとの違い
賃上げは「賃料アップ全体を含む概念」を指し、ベースアップも賃上げに含まれます。賃上げの中には、時限的な手当増額が含まれる場合も。一方、ベースアップは「社員全体の基本給の水準を引き上げること」を指し、基本的にはその後下がることはありません。
<ベースアップ>
- 賃金体系全体を引き上げる
- 基本給の賃金テーブル自体が上方修正される
- 将来的な賃金にも影響を与える永続的な変更
- 一度実施すると原則として減額は困難(労働者に不利益な変更にあたる場合)
<賃上げ>
- より広い概念で、賃金増加全般を指す
- ベースアップと定期昇給の両方を含む
- 臨時的な賃金アップを含むこともある
賞与との違い
賞与が「臨時的な支給」であるのに対し、ベースアップは「永続的な基本給の引き上げ」を指します。
<ベースアップ>
- 基本給に対する永続的な引き上げ
- 毎月の給与に反映される
- 退職金や各種手当の計算基礎となる
<賞与(ボーナス)>
- 一時的な支給
- 年に数回支給される(1回または支給しないことも)
- 業績連動型が多く、変動する可能性が高い
- 基本給とは別に計算される(基本給が算定の基になることはある)
ベアの種類
ベアは大きく分けて2種類あります。
<一律ベア>
全ての社員を同じ配分にする方法。同額を上乗せする場合と同じ昇給率で上乗せする場合があります。
- 同一金額(一定の金額を基本給に上乗せ)
基本給+上昇分の金額
基本給が低い人ほど上昇率が高くなります。
- 同一率(一定の昇給率を基本給にかけて算定)
基本給+(基本給×上昇分の割合)
基本給が高い人ほど上昇額が大きくなります。
<職種ベア>
職種(一般職や管理職など)や部署によって引き上げ条件を変える方法です。
企業がベースアップを行う目的
翌年度の賃金テーブルや労働条件を決めるために、2月~3月頃に労働組合と経営者で話し合いを行います。
労使交渉自体は企業ごとに行われますが、日本は3月決算の企業が多く、労働組合により有利な条件を引き出すために産業別の労働団体が足並みを揃えて同時期に交渉を始めます。この春に行われる労使交渉のことを春闘(春季生活闘争)といいます。
春闘については、人事担当者が知っておくべき2025年春闘の実態に関する記事もご参照ください。
ベースアップの相場(平均額と平均引き上げ率)
2025年春闘における賃上げの最新状況は、日本労働組合総連合会(以下、連合)の第3回回答集計(2025年4月1日時点)で以下のとおり報告されています。
- 平均賃上げ率(定期昇給+ベア):5.42%
- ベースアップ(ベア)部分:3.82%
- 賃上げ平均額:17,358円
この数値は前年(2024年)の同時期を上回り、1991年(賃上げ率5.66%)以来34年ぶりの高水準となっています。
ベア分が明確に分かる組合の集計においては、ベア平均額が12,274円(賃上げ率3.82%)となっており、連合が2015年にこの集計を始めて以降、最も高い数字となりました。
ベアの計算方法
ベアの計算方法は大きく分けて2種類あります。
・定額方式
全従業員の基本給に対して、同じ金額を一律に上乗せする方式です。
計算方法:昇給後の基本給 = 昇給前の基本給 + 定額昇給額
(例)
基本給が25万円の場合:25万円+2万円=27万円(上昇率8%)
基本給が50万円の場合:50万円+2万円=52万円(上昇率4%)
・定率方式
全従業員の基本給に対して、一定の割合を乗じて昇給額を算出する方式です。
計算方法:
昇給後の基本給 = 昇給前の基本給 +(昇給前の基本給×昇給率)
昇給後の基本給 = 昇給前の基本給 ×(1 + 昇給率)
(例)
基本給25万円、昇給率7%の場合:25万円×1.07=26万7,500円(1万7,500円増)
基本給50万円、昇給率7%の場合:50万円×1.07=53万5,000円(3万5,000円増)
ベアに関する法改正
個人(従業員)の所得水準を底上げする観点から平成25年度(2013年度)の税制改正で創設された「所得拡大促進税制」は、企業が給与等の支給額を増加させた場合(賃上げした場合)、その増加額について10%(中小企業は20%)の税額控除を認めるという、企業の賃上げを税制面から支援する制度でした。
その後、平成27年度・平成29年度・平成30年度に改正されながら制度は維持され、令和4年度に「賃上げ促進税制」と名称が変更され、制度内容も変わりました。
賃上げ促進税制は「物価上昇を超える持続的な賃上げ」を目指す観点から、令和6年度税制改正で3年間延長され(改正前2年間)、内容も拡充されています。従来の大企業のうち従業員数が2,000人以下の企業を「中堅企業」と位置づけ、大企業とは異なる要件を設定しました。
・大企業
3%の賃上げ率の要件はそのままに、段階的に7%まで賃上げ率の要件を創設し、より法人税を控除できるようになりました。
・中堅企業
賃上げ率が3%の時に10%税控除は大企業と変わりませんが、賃上げ率が4%の場合、大企業は15%の税控除、中堅企業では25%の税控除が適応されます。
※参照:中小企業庁「中小企業向け「賃上げ促進税制」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
ベースアップのメリットとデメリット
企業側からの視点からベースアップ(ベア)のメリットとデメリットを挙げてみます。
メリット
1. 採用力を高める、人材確保・社員の定着に効果がある
近年は新卒売り手市場と言われ、各企業は人材確保のために奔走しています。
適正なベアを続け「あの会社は今年も賃上げした」と就活生や転職者が考えれば、意欲がある人材が集まる可能性が上昇します。 特に物価が上がりつつある今、良い人材を採用するためには「安定した賃上げを行う企業という評判」が大きな武器になるのです。
すでに働いている社員にとっても、「この会社にいれば毎年給料が上がる」という安心感は定着率や帰属意識の向上につながります。
2. 社員のモチベーションが上がり、仕事の質が上がる
給料が上がれば誰でも嬉しくなるもの。モチベーションが上がった社員に積極的に仕事に取り組んでもらえれば業務の効率が上がり、仕事の質が上がることが期待できます。結果として企業の業績が上がり、社員に賃上げという形で還元できるという好循環が期待できるのです。
特に多くの生活用品が値上がりしている昨今、物価上昇分を補うベアは「会社が自分たちの生活を守ってくれている」と社員に感じてもらえるでしょう。
3. 会社のブランド力アップ
ベアをすれば、「安定した経営をしている」と企業のイメージアップにつながります。
「従業員を大切にする会社」「収支の状況が良好な会社」と取引先や顧客から信頼を得ることができ、新しい取引や案件をスムーズに進める下支えとなるでしょう。
デメリット
1. 人件費が固定費化してしまう
平成20年に施行された労働契約法によって労働条件の不利益変更は原則として従業員の同意が必要となったため、一度上げた基本給は下げにくいという点がベアの最大のデメリット。業績が良いからといってベアを実施してしまうと、業績が悪化した際には人件費という大きな固定費を抱えこむことになってしまいます。
2. 総人件費はベア以上に増える
ベアによる基本給アップは各種手当や残業代・賞与・退職金にも影響します。
たとえば基本給が3%上がれば、基本給を基に算定される残業代や賞与も同様に増加することになります。さらに社会保険料の会社負担分も増えるため、基本給の上昇率以上に人件費が増えてしまうのです。
「他社がやっているから」「業界が満額回答の雰囲気だから」という理由でベアを実施するのは早計です。自社の経営状況や見通しを分析して、適正なベア率を検討しましょう。
ベアに注目が集まる背景
なぜ今「ベースアップ」なのか?
1. 物価上昇へ対応する必要がある
近年の急速な物価上昇によって、給与の額面金額(これを名目賃金といいます)が同じでも生活は苦しい状況になりつつあります。
名目賃金を物価変動(消費者物価指数など)で調整したものを実質賃金といい、消費者の生活水準や購買力を反映したものになりますが、仮に年間給与が500万円から520万円に4%増加したとしても同時に物価が5%上昇すれば、名目賃金は増加しているものの実質賃金は低下しており、実際は購買力が減少してしまうのです。
厚生労働省が2025年2月に発表した「毎月勤労統計調査令和6年分結果速報」によると、2024年の実質賃金は現金給与額が前年比で2.9%の伸びを示しているにも関わらず、実質賃金は前年比0.2%と減少し、給与の上昇が物価上昇に追いついていないのが現状です。ベースアップは全従業員の基本給を底上げするため、物価上昇下での生活水準維持に欠かせません。
※参照:厚生労働省「毎月勤労統計調査令和6年分結果速報」(2025年2月5日)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r06/24cp/24cp.html
2. 消費を促すことで経済の好循環が生まれる可能性がある
ベースアップをすることで名目賃金が上がれば、消費するきっかけが生まれます。消費が拡大することで企業の収益が上がり、収益を投資に回すことで企業の成長速度が上がり、経済がよい方向に循環する可能性が高まるのです。
3.政府による後押し
ベアに関する法改正で触れたように、税制が改正され要件が緩和されたことにより、より一層賃上げをしようという企業が注目しています。賃上げ促進に加え、教育訓練費を増やしたり子育てと仕事の両立支援に積極的な企業へは控除額を上乗せしたりといった措置も、ベースアップを実施するきっかけになっています。
近年のベースアップ実施状況
ベースアップの相場(平均額と平均引き上げ率)で述べたとおり、2025年は1991年(賃上げ率5.66%)以来34年ぶりの高水準となっています。2020年~2024年の連合の調査結果を見ると、ここ数年で賃上げ率、賃上げ額とも急激に伸びていることが分かります。現在の物価高を考えると、数年はこの水準が維持されるのではないでしょうか。
- 2024年
平均賃上げ率(定期昇給+ベア):5.10%
ベースアップ部分:3.56%
賃上げ平均額:15,281円
- 2023年
平均賃上げ率(定期昇給+ベア):3.58%
ベースアップ部分:2.12%
賃上げ平均額:10,560円
- 2022年
平均賃上げ率(定期昇給+ベア):2.07%
ベースアップ部分:0.63%
賃上げ平均額:6,004円
- 2021年
平均賃上げ率(定期昇給+ベア):1.78%
ベースアップ部分:0.55%
賃上げ平均額:5,180円
- 2020年
平均賃上げ率(定期昇給+ベア):1.90%
ベースアップ部分:0.50%
賃上げ平均額:5,506円
わが社はベースアップすべき?しなくても大丈夫?
ベアする場合の注意点
手続きが必要
ベア(賃金表)変更時には、以下のような法的な手続きが必要となります。
- 賃金表が改訂されるため、労働組合(または労働者の過半数)の同意が必要になります
- 新しい賃金表に変更した就業規則を労働基準監督署への届け出る必要があります
- 労働者への周知:変更内容を必ず労働者全体に周知する義務があります
企業財務への影響と注意点
ベアは企業全体の賃料体系を変更するため、企業財務に大きな影響を与えます。
- 基本給(1日当たりの賃金)を基に算定する残業代や休日出勤手当などの他の手当や社会保険料などの福利厚生費にも影響します
- ペースダウン(基本給を下げること)は労働者から同意を得ることが難しいため、ベアは一度実施すると撤回が困難です。継続的に賃金増加分の原資を確保できるか検討する必要があります。
ベアしない場合の対処法
ベアが難しい場合でも、他の形での還元策はあります。
基本給ではなく、手当(福利厚生)として支給
基本給は一度上げてしまうと下げるのは難しくなってしまいますが、手当の場合、あらかじめ支給する期間や条件を定めて、一時的に支給することができるようになります。
賞与での還元
就業規則で規定した通常の賞与とは別に、業績が好調の場合や決算などの特別な機会に追加で支給するなど柔軟に対応することができます。
選択型給付(カフェテリアプラン)の導入
カフェテリアプランとは、従業員が自分で必要なサービスを選択できる福利厚生サービスのこと。従業員自身が本当に必要とするサービスを選べるため、一律で同一の福利厚生を取り入れるよりも社員に寄り添う姿勢を示すことができます。
人手不足が騒がれ優秀な人材を確保することが難しい今、ベアしないのであれば福利厚生を拡充するといった対策で従業員との関係性を保ち、満足度を向上させる創意工夫が求められています。
|
★年間12,000円~/人でベースアップ対策! |
幅広い種類の福利厚生を拡充できる
福利厚生サービス ベネフィット・ステーション

従業員満足度を高めるためには、福利厚生を幅広く用意する必要があります。
とはいえ、福利厚生を1から自前で整えるのは大きな労力がかかります。
そんなときに活用したいのが福利厚生サービスです。
ベネフィット・ステーションではレジャー・食事・育児・介護・財産形成といった幅広い福利厚生を一気に拡充することができます。
また、ベネフィット・ステーションは、
・一業者との契約で140万件以上のサービスが使えるようになる
・会員数は業界最大規模の1,220万人(※)が導入済
・導入企業法人数約18,100団体
(※2025年4月時点 ※福利厚生、CRMおよびパーソナルの合計会員数)
従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどないのも特徴です。
ぜひこの機会に福利厚生制度の拡充を検討していきましょう。