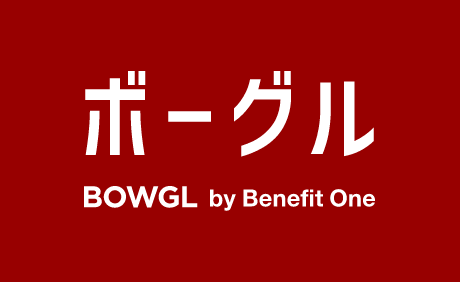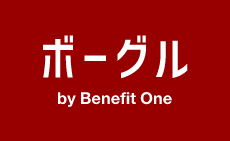【最新版】企業担当者が知っておくべき介護休暇と介護休業との違い

高齢化がすすむ中、親や家族のためにやむを得ず仕事を離れる「介護離職」が増加しており、社会問題となっています。
その背景にあるのは、「2025年問題」です。
いわゆる「団塊の世代」は、すでに70代に突入しており、2025年には後期高齢者(75歳)に達します。
介護と仕事の両立に直面する従業員が、少子化や家族構造の変化により、一層増加する見通しです。
こうした状況を踏まえ、従業員のためにつくられた制度として「介護休暇制度」と「介護休業制度」があります。
両制度ともに家族の介護のために活用できる制度ですが、活用できる対象や条件などの違いがあり、企業はこれらの制度をスムーズに活用できるように、準備をしておく必要があります。
そこで今回は、介護休暇制度と介護休業制度の違いについて説明します。
もしもこの記事をご覧いただいている方の中で、自社の福利厚生制度についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずはじめに「企業担当者必見!「福利厚生サービス」のおすすめ5選を解説」の記事をお読みください。
福利厚生のアウトソーシングについて 福利厚生の充実は、従業員満足度を向上させ、採用や離職防止にも役立ちます。 総合福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」は ・140万件以上のサービスが利用できるため、年齢や性別関係なく、従業員の多様なニーズに応えることができる ぜひこの機会にご検討ください。
・福利厚生会員数は業界最大級の1,100万人(※2024年4月現在)
・「福利厚生」「健康支援」「教育・研修」をサポート
目次
介護離職を防ぐための両立支援

家族の介護や看護を理由とする離職者は、年間約10万人にのぼります。
仕事と介護の両立に不安を感じる従業員も決して少なくはありません。
その一方で、従業員の仕事と介護の両立の実態について、把握できていない企業が多いことも事実です。
企業にとって、まずは、従業員の実態把握をすることが必要になります。
また、優秀な人材が介護により離職するといった状況に直面する前に、介護と仕事の両立を支援する体制づくりや休暇制度が利用しやすい職場作りをおこなう必要があります。
そのためにも国の制度や最新の情報を常にチェックしておかなければなりません。
介護休暇と介護休業の違い

介護休業と介護休暇は、「育児・介護休業法」により定められている制度です。
どちらも要介護状態の家族を介護するために活用できる制度ですが、ここでは、両制度の違いについて説明します。
取得可能な日数
取得可能な日数は、介護休暇と介護休業で大きな違いがあります。
【介護休暇】
・介護が必要な家族1人につき、1年で5日間取得が可能。
・対象家族が2人以上の場合は、1年で最大10日間取得することができる。
【介護休業】
・要介護状態の家族1人につき、通算93日間取得が可能。
・93日間を最大3回に分割して取得することができる。
対象となる労働者の条件
対象となる労働者は、両制度ともに、対象家族を介護する労働者(日雇い労働者を除く)となります。
介護休業の場合、有期雇用労働者については取得要件が別途あります。
[有期雇用労働者の取得要件]
・同一の事業主に1年以上雇用されていること。
・介護休業開始予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約期間の満了し、更新されないことが明らかでないこと。
対象となる家族
対象となる家族は、制度間の違いはありません。
・配偶者(事実婚も可能)
・実父母
・配偶者の父母
・法律上の親子関係がある子(養子を含む)
・祖父母
・兄弟姉妹
・孫
給付金制度
給付金は、介護休暇の場合はありません。
介護休業の場合、支給条件に当てはまる場合に支給されます。
育児・介護休業法改正による変更点

令和元年12月に改正された「育児・介護休業法」が令和3年1月に施行されました。
この改正により、以下の内容が主に変更されました。
時間単位での取得が可能に
介護をおこなう労働者が、半日単位で取得可能だった介護休暇を時間単位での取得が可能になりました。労働者の申し出により、労働者が希望する時間数を取得できます。
政府が「中抜け」を後押し
「中抜け」とは、就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることをいいます。今回の改正では、企業へ、この「中抜け」ありの休暇取得を認めるように配慮するよう求められています。
原則すべての労働者が取得できる
対象労働者であれば、1日の所定労働時間に関わらず、すべての労働者が取得できるようになりました。
※参考:⼦の看護休暇・介護休暇が 時間単位で取得できるようになります︕
介護休業給付金制度の活用と申請方法

介護給付金の活用と申請方法について詳しくご説明します。
介護休業給付金の支給条件
以下の条件に当てはまる場合、介護休業給付金が支給されます。
・雇用保険の被保険者で、介護休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上ある方。
・介護休業期間中の賃金が、「賃金月額」もしくは「賃金日額×支給日数」の80%未満であること。
・支給単位期間(介護休業開始日から起算した1か月ごとの期間)の就業日数が10日以下であること
・有期雇用労働者は上記の条件に加えて、介護休業開始予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約期間の満了し、更新されないことが明らかでないこと。
※参考:介護休業給付の内容及び支給申請手続きについて | 厚生労働省
介護休業給付金の申請方法
介護休業給付金の手続きは、基本的に勤務先の企業が公共職業安定書(ハローワーク)に必要書類を提出する形となります。
申請に必要な書類は以下の通りです。
・介護休業給付金支給申請書
・従業員が企業に提出した介護休業申出書
・休業開始時賃金月額証明書
・介護対象家族の方の氏名、従業員との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等)
・賃金台帳や出勤簿 ※企業が記録している書類を添付してください。
・支給希望口座のコピー(不要な場合もあります)
介護休業給付金の支給額
支給申請の結果は、支給額等が記載された「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」により通知されます。
支給金額は、原則として以下の計算式で計算します。
介護休業給付金 = 休業開始時の賃金日額 × 支給日数 × 67%
・支給日数とは、介護休業を利用した日数です。
・休業開始時賃金日額とは、介護休業開始前から6ヶ月間の合計賃金額を180日で除した金額になります。
介護休業給付金制度活用のポイント
多くの企業では、介護休暇期間は無給であるため、会社は介護離職を防ぐためにも介護休業給付金制度の活用をサポートする必要があります。
制度を有効活用するためにも、会社として常に最新で正しい情報を把握しておくことも必要です。
まとめ

高齢化がすすむ中、介護に直面する社員が増えることは間違いありません。
介護休暇制度や介護休業制度については、法改正が適宜おこなわれています。
社員のサポートをおこなうためにも、最新の情報をチェックしておくようにしましょう。
※参考:介護休業制度|厚生労働省
※参考:ハローワークインターネットサービス – 雇用継続給付
ワークライフバランスの充実を支援する
福利厚生サービス ベネフィット・ステーション

待機児童問題/介護離職者の増加など、ワークライフバランスを取り巻く環境には問題が山積しています。
フレキシブルな勤務形態、休業・休暇制度を整えることは大前提として必要ですが、それだけでは育児・介護にかかわる金銭の問題や情報の提供不足といった課題が残ります。
福利厚生サービス ベネフィット・ステーションの導入により上記の課題を解決することができます。
①【育児】保育園探しのお手伝いや認可外保育施設利用時の割引等があり、保育と仕事の両立を支援できる。
②【介護】介護情報の無料提供・無料相談、介護用品購入費用の一部還付を受けられ、介護離職を防止する。
また、従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどありません。
ぜひ人事制度の改定と併せて福利厚生制度の拡充を検討していきましょう。