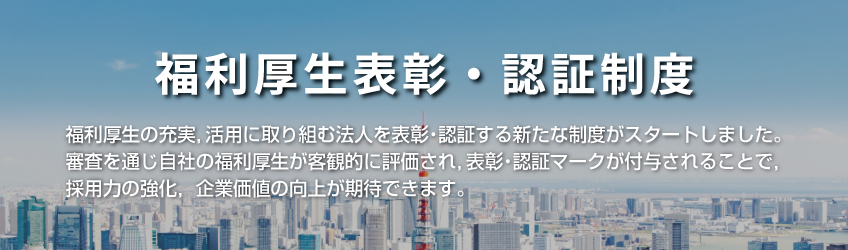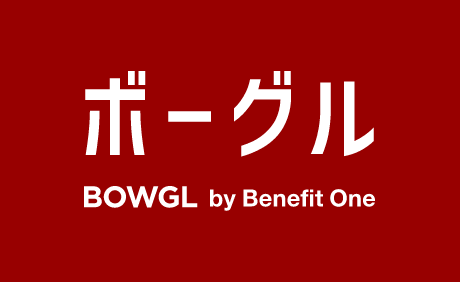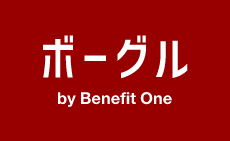「インフレ手当」とは?導入企業・金額相場と代替案【事例アリ】

インフレ手当とは
インフレ手当とは、従業員の生活を支援することを目的として、企業が従業員に支給する特別手当です。
企業がインフレ手当の支給に踏み切った背景には、文字通り、国内において急激な物価上昇が進んだことで、従業員の生活に影響が出ている状況があります。
こうした状況に対応し、日常生活における従業員の負担を少しでも軽減するために、すでに多くの企業がインフレ手当の支給を始めており、今後もインフレ傾向が続くとの見方が強まる中、その取り組みに改めて注目が集まっています。
本記事ではインフレ手当の概要、メリットと注意点について解説します。
インフレ手当の支給パターン
すでにインフレ手当を支給している企業を見ると、そのパターンは大きく2つに分類することができます。ここでは、それぞれのパターンの特徴について解説していきます。
一時金による支給
毎月支給される給与以外に、給与への一時的な上乗せまたは賞与に上乗せすることで、手当を支給する方法です。既存の給与や賞与の支給手続きと合わせて行うことで、事務処理の手間が増えないメリットがある一方、一時的な支出が大きくなることで企業のキャッシュフローが悪化してしまうおそれもあるため、注意が必要です。
月額手当による支給
毎月の給与に一定額を上乗せして支給する方法です。一時金による支給と比べて、一度にまとまった金額を支払う必要がないため、手当を支払う企業にとってはキャッシュフロー面で負担になりにくいといえます。しかし、実質的な給与改定と見なされるため、就業規則のうち「賃金の決定、計算に関する事項」を改定する必要があるなど、手続き面での負担が多いというデメリットもあります。
【無料DL】インフレ手当とは
インフレや物価高が叫ばれるなか、インフレ手当を支給する企業が増えています。
インフレ手当とは何か、また現金の支給以外でもできる従業員の生活をサポートする方法をまとめています。
採用力・定着率アップにつながるサービスのご紹介も記載しております。
・インフレ手当についての解説 
・現金以外のインフレ手当について
無料で資料ダウンロードが可能です。ぜひご覧ください。
インフレ手当を支給した企業とその相場
インフレ手当を支給している主な会社と、全国の相場をご紹介します。
インフレ手当を支給した主な企業
インフレ手当を支給した主な企業とその支給額は以下のとおりです。
- 三菱自動車工業株式会社…一時金(正社員:3万円/非正規従業員:7万円)
- ヤマハ発動機株式会社…一時金(一律5万円)
- 三菱製鋼株式会社…一時金(一律5万円)
- 三菱ガス化学株式会社…一時金(扶養家族数に応じて3~6万円)
- 日本特殊陶業株式会社…一時金(正社員:5万円/契約社員・パートタイム社員:2万円)
- YKK AP株式会社…一時金(一律5万円)
- サイボウズ株式会社…一時金(労働時間に応じて6~10万円)
- 株式会社すかいらーくホールディングス…一時金(正社員:子どもの数に応じて5~12万円/パートタイム社員(社会保険加入):1万円)
- ケンミン食品株式会社…一時金(勤続1年以上:5万円/勤続1年未満:在籍日数に応じて1~3万円)
- 大東建託株式会社…一時金(2023年3月31日までに入社:10万円/2023年4月1日以降に入社および時給者:1万円)
- ダイコク電機株式会社…一時金(正社員:3万円/契約社員・パートタイム社員:1万5,000円)
- 株式会社ノジマ…月例手当(1万円)
- 株式会社コロプラ…月例手当(1万円)
- オリコン株式会社…月例手当(1万円)
- 株式会社イートアンドホールディングス…月例手当(8,000円)
※参照:
キノシタ社会保険労務士事務所「インフレ手当」
https://www.kisoku.jp/jouhou/inflation.html
株式会社エフアンドエム 中小企業総合研究所「中小企業の冬季賞与及びインフレ手当に関する実態調査」(2023年2月)
https://www.fmltd.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/02/20230226.pdf#page=6
インフレ手当の平均支給額
インフレ手当の支給額については、(株)帝国データバンクが「インフレ手当に関する企業の実態アンケート」の調査結果を2022年11月に公表しています。
この調査結果によると、インフレ手当を一時金として支給している企業における平均支給額は、5万3,700円。内訳をみると、「1万円~3万円未満」が27.9%で最も多い結果となっています。
これに対し、月額手当として支給している企業では、平均支給額は6,500円でした。内訳をみると、「3千円~5千円未満」と「5千円~1万円未満」が同率で最も多い結果となっています。
なお、同調査ではインフレ手当の支給状況についてのアンケート結果も含まれており、従業員に対してインフレ手当を「支給した」「支給を予定している」「支給を検討している」と回答した企業は全体の26.4%で、全体の4社に1社がインフレ手当に前向きという実態が見えます。
※参照:株式会社帝国データバンク「インフレ手当に関する企業の実態アンケート」(2022年11月)
https://www.tdb.co.jp/report/economic/ltgj1cyg_v8/
【プロが解説】インフレ手当は支給すべき?リスクはある?
インフレ手当への注目が高まる中、自社でも支給すべきなのか悩む経営者や人事担当者の方もいるでしょう。
そこで、インフレ手当の意義やリスクについて、日本における福利厚生研究の第一人者である山梨大学名誉教授・福利厚生戦略研究所代表の西久保浩二氏にお伺いしました。
 |
プロフィール 西久保 浩二(にしくぼ こうじ)氏 1958年大阪府生まれ。神戸大学卒業後に大手生命保険会社での勤務を経て生命保険文化センター主席研究員を務める傍ら、筑波大学大学院修士・博士課程を修了。博士課程単位取得後には東京大学客員准教授などを経て2007年山梨大学教授就任、2024年名誉教授。現在は福利厚生戦略研究所代表を兼務。 「国家公務員の福利厚生のあり方に関する研究会(総務省)」座長、「福利厚生表彰・認証制度」審査委員長など多数の公職・関連部会委員を歴任。現在、「ワーキングケアラーに関する研究会」(内閣府)委員。『戦略的福利厚生の進化』、『わが国の福利厚生の導入と利用の実態とその諸要因、そして有効性の検証』などの著書がある。 |
インフレ手当の効果は一時的かつ一過的
インタビュアー(以下、「イ」):インフレ手当という言葉がよく聞かれるようになりましたが、施策としての評価はいかがでしょうか。
西久保浩二氏(以下、「西久保氏」):インフレ手当は今流行の手当てといわれていますが、支給した企業は1割程度、支給を考えている企業も合わせると3割弱くらいとなっています。物価高騰に困っている社員に一過性の手当を出すべきなのかどうかについては、多くの企業が慎重派というところですね。
インフレ手当は福利厚生としての支給手当の一種なので、企業側の意思で停止することも比較的容易です。例えば、就業規則に「物価水準2%上昇の際のみインフレ手当を支払う」と定めていれば、1.5%になると支給停止できるのです。
インフレ手当は一時的に本当に生活に困っている社員を救済するという意味では有効ですが、継続的な恩恵のあるベアのほうが従業員にとっては良い施策といえます。
インフレ手当には法的縛りが発生する
イ:インフレ対策として手当を支給する場合、注意すべきポイントはありますか?
西久保氏:インフレ手当は賃金扱いになります。賃金には賃金支払い5原則(※)をはじめとした法的縛りが多くあり、適当に払うことはできません。「公的な政府発表の物価上昇率2%を超えたら支給する」などの規程を作り、就業規則に明記しなければなりません。これを絶対的記載事項といいます。また、従業員には税金・社会保険料の負担増ともなります。
このような点も理解したうえで、よく考えて設計することが必要です。また、不利益変更ができなくなることにも注意しなければなりません。
※賃金支払い5原則…通貨で・直接・全額を・毎月1回以上・一定の期日を定めて支払われなければならないという労働基準法第24条の規定
参照:厚生労働省「労働基準行政全般に関するQ&A」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei05.html
インフレによる課題を解消できるなら、方法は手当に限らない
イ:現金以外の手段でインフレ手当の代わりとするならば、どのような手段が有効だとお考えですか?
西久保氏:手当は一時的には社員に喜ばれますが、当然ながらベアのほうが有益なので、導入については何を狙って実施するのかを社員とよく議論する必要があるでしょう。ほかにも代替策は数多くあります。
イ:今ならお米5㎏でも話題になりそうですね。(取材時期は2025年5月)
西久保氏:コストは安いがインパクトがありますね。手当ではありませんが、ガソリンや固定費の割引、健康、学習などが選べる福利厚生サービスも代替策として有効です。社員がどうしても毎月払わなければならないものを安く手に入れられるからです。
イ:衣食住にまつわるものを福利厚生として優先的に提供すれば、直接のインフレ手当でなくても従業員の満足度を上げられるかもしれないということですね。
西久保氏:そうです。福利厚生はその内容や支給方法で条件を満たす限り給与課税されないため、社員にとってはきちんと計算すると安心できるメリットになります。ただ、「福利厚生の生計費支援のような衣食住に対する施策は、物価高に大きなメリットがある」と説明しないと、従業員の多くが十分に理解していないかもしれませんね。
福利厚生を賢く活用すれば、今の物価高に対して生活に本当に役立つ支援ができる。これを社員に理解してもらうことが重要です。
イ:結局、インフレ手当で収入が増えると税金も増える。そう考えると、福利厚生のほうがありがたい制度なのかもしれませんね。
西久保氏:ベアで額面賃金が上がれば、控除額や社会保険料も比例して上がってしまう。生活にとって必需性の高い福利厚生は、総合的に考えると現金で貰うよりメリットが大きいと思います。
昨今では人手不足もあり「給料を上げる」という流れになっていますが、上げる側も受け取る側も最善策がそれしかないわけではありません。福利厚生やほかの給付、働きやすさも含め、「だけ」に固執することのリスクもよく考え、労使ともにwin-winになる方法をクレバーに比較検討することが大切です。
インフレ手当を支給する3つのメリット
企業にとって従業員にインフレ手当を支給するメリットは少なくありません。ここでは、そのうち主な3つのメリットを解説していきます。
メリット1 従業員満足度の向上
企業の労働生産性を上げ、業績向上につながる指標として、従業員満足度の重要性は近年ますます高まっています。そんな従業員満足度を向上するためには、従業員の不満・不安に寄り添うことが欠かせません。
その点、インフレという世情に対して、企業が従業員のサポートを行うという意思を見せることのできるインフレ手当は、従業員満足度向上につながりやすいと言えるでしょう。
メリット2 採用強化・離職率の軽減
少子高齢化により生産年齢人口の減少の続く中、多くの企業は人材確保という課題に直面しています。インフレ手当は、こうした課題を解消する取り組みとしても効果を発揮します。
前述したように、インフレ手当の支給により従業員満足度が向上すれば、離職率の軽減につながることが期待されます。また、そのような取り組みを実施していることを求人の際にPRすることで応募数増につなげるなど、採用力の強化も期待できます。
メリット3 企業のイメージアップ
このところ、消費者が購買行動をする際の判断基準として、商品やサービスの機能や性能はもちろん、企業の信頼性を重視する傾向が加速しており、企業にとってイメージ戦略の重要性が高まっています。
従業員の不安に寄り添う取り組みとしてインフレ手当を実施しているということが消費者の目に触れれば、採用面だけでなく、企業全体のイメージとしてもプラスになるでしょう。最近では、SNSを通じて企業が行う取り組み情報を広めやすくなっているため、そうしたツールを活用することで、さらなるイメージアップを図ることも可能です。
インフレ手当の注意点とは
ここまで、インフレ手当の概要やメリットについて紹介してきました。一方で、インフレ手当の支給時には注意しておきたいポイントもあります。ここでは、主な3つの注意点を解説していきます。
税金や社会保険の負担が増える
一時金または月額で支給する場合のいずれも、現金でのインフレ手当の支給は、従業員の給与所得および社会保険の報酬として見なされます。そのため、支給する金額によっては、税金や社会保険料の負担が従来よりも高まってしまう可能性があります。
そのため、企業の中には、現金支給以外の方法によるインフレ手当を導入しているケースもあります。具体的には、福利厚生で受けられるサービスを拡充するといった手法が挙げられます。
支給方法によって、就業規則を変更する必要がある
インフレ手当を月額手当として支給する場合、また、一時金であっても既存の賞与とは別の名目で支給する場合には、就業規則のうち「賃金の決定、計算に関する事項」を改定する必要があります。
そして、就業規則を変更する際には、所轄の労働基準監督署への届出、労働組合または労働者の過半数を代表する者の意見書の作成などが必要です。そのため、よりスピード感を持ってインフレ手当の支給を検討している場合には、一時金として賞与に上乗せするか、前述したように福利厚生の拡充といった取り組みを採用することがおすすめです。
継続的な支給が必要となる可能性も踏まえておく
今後、インフレ傾向が長期化した場合には、一時的なインフレ手当の支援では従業員への経済的サポートの効果が十分でなく、継続的な支給が必要となる可能性があります。インフレ手当の支給額を決める際には、そうした可能性も踏まえておくことが大切です。
また、世情によっては、一度支給したインフレ手当を継続しないことが、従業員の企業への不信感につながってしまう可能性もあります。そうしたケースを避けるためにも、インフレ率などを参考に、自社のインフレ手当支給基準を明確にしておくと良いでしょう。
インフレ手当の代替案となる「福利厚生代行サービス」とは
インフレ手当は支給方法によって就業規則を変更する必要があるため、スピーディな対応が困難です。また、インフレ手当支給によるコストが経営を圧迫する可能性があるため、十分な注意が必要です。
こうした懸念を払しょくし、インフレ手当の代替案として有効なのが「福利厚生代行サービス」。就業規則や賃金制度の変更が不要で迅速に導入できるうえ、手当支給よりもコストを抑えられます。
株式会社ベネフィット・ワンの総合型福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」では、グルメやレジャーのほか、ショッピングなど日常生活の様々なシーンで利用できる特典・割引を提供しています。従業員はサービスを活用することで生活費の負担を軽減し、毎月の可処分所得を増やすことが可能です。提供するサービス内容は従業員のニーズに応じて設計できるため、効率的に従業員の満足度向上を目指せます。
「ベネフィット・ステーション」の導入企業は、電気・ガス代、通信費、住宅費などの日常生活に関わるサービスを給与天引きにより決済できる「給トク払い」も無料でご利用いただけます。
従業員はより割安な価格でサービスを利用できるうえ支払い管理が不要になるというメリットもあるため、手当以上の恩恵となるでしょう。
また、「ベネフィット・ステーション」では、パート・アルバイト従業員を対象に最大50%オフ(※)で福利厚生サービスを提供する「パート・アルバイト割」もご用意しています。
パート・アルバイト従業員を多数雇用している企業の場合、全員にインフレ手当を支給するとなると相当な負担が掛かります。「パート・アルバイト割」をご活用いただければ、パート・アルバイト従業員に対しての福利厚生を大きなコストをかけずに導入できます。
パート・アルバイト従業員には、扶養控除内で働く方も多くいます。そのような従業員にとって、賃金外での経済的メリットは大きく歓迎されるでしょう。従業員エンゲージメントの向上をもたらし、ひいては離職防止効果、採用力向上も期待できます。
※パート・アルバイトの平均就労時間と正社員比率に応じて割引
福利厚生サービスは、インフレ手当よりお得?導入企業の声

警備業界の大手企業として知られているセントラル警備保障株式会社は、警備から防犯・防災まで総合的なセキュリティサービスを全国展開しています。
同社は、福利厚生の充実をさせるために2025年3月にベネフィット・ステーションを導入しました。導入してから現在までのプロセスを振り返るとともに、導入後の変化や効果などについて、寺田部長と担当の柴山様にお話を伺いました。

執行役員 人事総務本部 総務部長 兼 法務審査部長 寺田 様
福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を選んだ理由
イ:ベネフィット・ステーション導入前は、どのような福利厚生を実施していましたか?
寺田氏:千葉と和歌山に所有している保養所に加えて、レジャー施設やスポーツクラブの優待が主な福利厚生でした。宿泊補助や利用割引などで利用価値を高めていました。
イ:利用状況はいかがでしたか?
寺田氏:全体的に見て、利用率はふるいませんでした。例えば千葉県の保養所を利用する社員は全体の0.8%程度で、稼働日も年15日とテコ入れが必要な状態でした。
加えて、利用する社員に偏りが出たことも課題でした。利用できる施設が関東圏に集中していたため、地方支社の社員は福利厚生の恩恵を受けづらかったです。
例えばスポーツクラブは建物が特定のエリアに立地しており、主に利用するのは日常的にアクセスする社員に限られてしまいました。弊社の全社員のうち7割が関東圏に在住・在勤していますが、すべての社員に公平に提供できてこそ福利厚生だと考えているので、改善の必要性を感じていました。
イ:最終的にベネフィット・ステーションに決められた理由は何ですか?
寺田氏:地方に住んでいても利用できるサービスが豊富で、社員個人が自分で選べる点に魅力を感じました。
加えて、若年層向けのサービスが多かったことも魅力的でしたね。特にNetflix(ネットフリックス)は訴求力が高いサービスだと思いました。
警備業界において、若手の人材確保は慢性的な課題。福利厚生を充実させれば、若者の求人を増やしたり離職率を下げたりできるのではと期待しました。

人事総務本部 総務部 課長代理 柴山 様
イ:他社サービスと比較検討はされましたか?
柴山氏:正直に申し上げて、ベネフィット・ワンさん一択でした。Netflixのプラン内容や費用感も良く、選ばない理由はどこにも見当たらなかった、というのが率直な気持ちです。
他社との比較資料も見たのですが、ベネフィット・ワンさんに匹敵するサービスがなかったため、早い時期に決定しましたね。
イ:ベネフィット・ステーションの導入にあたり、工夫された点や苦労された点があれば教えてください。
寺田氏:まず、経営層に提出する資料作成の前に自分たちがサービスへの理解を深める必要がありました。また、その良さや効果をいかに端的に資料にして伝えるかについても頭を悩ませましたね。
こちらは良いと思っても、経営層がそう思わなければ導入にはつながりません。正確に伝えられるように、サービスのメリットとデメリット、サービス導入のビフォー・アフター、そして新卒が会社に求めていることといった点に絞り込んでアピールしました。
イ:資料をご覧になった経営層の方々の反応はいかがでしたか?
寺田氏:反対意見はほとんど出ず、概ね好意的に受けて止めてもらえました。「新卒者の採用」といった経営層が抱えている課題を解決できるという可能性を示せたのが良かったのかと思っています。Netflixは若者の興味を引くサービスであるという点も、社長は柔軟に理解してくださって、最終的に導入が決まった時はホッしました。
利用率向上のために行ったこと
イ:ベネフィット・ステーションの利用率について、目標は設定されましたか?
寺田氏:「今年中に初回ログイン率を65~70%にする」という目標を立てました。
現時点(2025年7月/導入開始から3ヶ月強)で社員の登録率が56.5%なので、達成できない数字ではないと思います。宿泊施設から水族館、映画、ショッピングなどさまざまなサービスを利用できるので、何かを買ったり利用する時に「これはサービス対象かどうか」の確認を習慣化する社員が増えれば、利用率も増加すると踏んでいます。
イ:やはり導入開始時が肝だと思うのですが、ベネフィット・ステーションの利用率を上げるために行った施策を教えてください。
柴山氏:ベネフィット・ワンさん主催のカンファレンスに出席したときに、チラシを作ったら効果があったことを他社から聞き、当社でもやってみることにしました。
チラシには、割引率の高いお店の紹介や、加入すれば付与されるベネポの使い道についてもアピールしました。「社員が利用したくなる情報」を厳選し、Netflix利用についての案内も含めました。
ベネフィット・ワンさんの協力を得て、ベネフィット・ステーションの利用促進動画も作成しました。シナリオは寺田が書き、私と寺田の2人がベネフィット・ステーションの利用価値についてお喋りするという内容です。
イ:動画まで!面白い施策ですね。反響はいかがでしたか?
柴山氏:チラシの効果は高く、9日間で50人増えました。
動画については視聴率までは把握できていませんが、視聴した社員から「寺田部長って結構面白い方なのですね」といった感想が寄せられました。本社の部長がここまで頑張っているのか、という印象を社員に与えられたので、ベネフィット・ステーションの周知に貢献できたと思います。

イ:施策を行う中で、苦労されたことがあれば教えてください。
寺田氏:Webサービスを利用しない社員が一定数いまして、この層をどのようにしてサービス登録まで持っていくかで頭を悩ませています。サービスの良し悪し以前の問題なので、難しいですね。例えば入社時に登録する時間を設けるなど、ログインのハードルを下げる機会を作ることも検討しています。
また、利用してもらうにはまず知ってもらうことが大前提になりますが、こちらについても苦労しましたね。
イ:確かに、認知されなければ利用はされないですものね。
どのような活動が結果に結びついたと思いますか?
寺田氏:本社と支社の担当者が連携して、地道に周知活動を行ってきたことだと思います。
定期的に行っているのは、会社全体の利用状況の確認です。月に一度ベネフィット・ステーション利用状況を確認していますが、各支社の担当者からの質問に回答したり、利用促進について話し合ったりしています。
こうした活動が功を奏したようで、導入時は30%ほどだった利用率が、4か月後には55%を超えていました。
福利厚生サービスは「インフレ手当」に勝る?従業員の反響は
イ:ベネフィット・ステーションが「インフレ手当」の代わりだと考えると、具体的にはどのような点が有用だと感じられますか?
寺田氏:インフレに伴う従業員の生活支援をするために、インフレ手当を支払う企業もありますよね。ベネフィット・ステーションにおいては、毎年付与されるベネポ5,000ポイントがインフレ手当に相当すると思います。
さらに、さまざまな店舗や施設の料金が通常よりも安くなったり、買い物でポイントが貰えたりします。例えば、食費を削減するために割引対象のレストランを選ぶ。映画館に行くのを我慢してNetflixで映画を観るというふうに、好きなサービスを利用するだけで生活費を抑えられます。一時保育の補助金といった育児介護サービスも含まれており、従業員の生活支援として時間価値が非常に高いと思います。
ベネフィット・ステーションは、日常生活で使えるシーンが非常に多い。ベネフィット・ワンさんからは「上手に使えば年間15万円ほど支出を抑えられる」と聞いています。会社側からすると従業員の給料を1,000円上げるのも大変なのですが、ベネフィット・ステーションなら導入するだけですべての社員が生活形態や趣味に合わせて好きなサービスを選んで恩恵を受けられる。インフラ手当として、十分機能すると考えています。
イ:ベネフィット・ステーションの導入の効果を教えてください。
寺田氏:Netflixを利用していなかった社員からの反響が大きく、ログインするだけで毎年もらえるベネポ5,000ポイントも非常に喜ばれました。こうした反応を見ると、導入前よりも従業員満足度が向上していると思います。
また、Netflixを無料で利用できることは求人において大きなアピールポイントになるので、採用力もアップしました。転職フェアに出展したときに「Netflixが見放題の福利厚生アリ!!」といった形で前面にアピールしていたら、テレビ局から取材を受けたこともあるんですよ。
さらに、ベネフィット・ステーションが提供している育児介護サービスによって、課題だったワークライフバランスの改善にもつながっていると実感しています。
イ:ベネフィット・ステーションについてどのように思っていますか?
柴山氏:非常に利用度の高いサービスだと思っています。個人的な意見ですが、ベネフィット・ステーションを導入してから毎日ワクワクすることが増えました。何か買い物をするときに、「サービス対象に入っているかな」と確認して、対象内だと「やった!」という気持ちになりますね(笑)。
寺田氏:私は楽天ユーザーなので、例えば楽天トラベルでサービス対象のホテルを予約すると、ベネポと楽天ポイントの両方をもらえるのが嬉しいです。
イ:今後の人事・人材戦略としての展望や実現したいことなどがあれば教えてください。
寺田氏:社員のQOLを上げて生産性を向上させ、会社の実力の底上げを図りたいです。
好きなサービスをお得に利用できたり、使い勝手の良いポイントを貯めたりできるベネフィット・ステーションは、働くモチベーションの底上げにつながると考えています。
イ:今後、ベネフィット・ワンに期待していることを教えてください。
寺田氏:今のままでも十分に満足していますが、強いて言うならNetflixのような万人受けしやすいサービスへの拡大や割引率の向上があるとありがたいですね。
また、全体的なコストを下げる意味で、借り上げ社宅の手配といった他の福利厚生についてもワンストップで対応できるプラットフォームを提供していただけたらいいなと思います。
福利厚生サービスの活用は、企業にも従業員にも大きなメリットがあります。
以下の資料では、インフレ手当のメリットや課題とその解決策について詳しく解説しています。賃上げ以上に効果的な施策についてもご案内しているので、ぜひ無料でダウンロードしてお役立てください。
幅広い種類の福利厚生を拡充できる
福利厚生サービス ベネフィット・ステーション

従業員満足度を高めるためには、福利厚生を幅広く用意する必要があります。
とはいえ、福利厚生を1から自前で整えるのは大きな労力がかかります。
そんなときに活用したいのが福利厚生サービスです。
ベネフィット・ステーションではレジャー・食事・育児・介護・財産形成といった幅広い福利厚生を一気に拡充することができます。
また、ベネフィット・ステーションは、
・一業者との契約で140万件以上のサービスが使えるようになる
・会員数は業界最大規模の1,220万人(※)が導入済
・導入企業法人数約18,100団体
(※2025年4月時点 ※福利厚生、CRMおよびパーソナルの合計会員数)
従業員が企業担当者を介さずサービスの利用申し込みを行うため、導入後の事務作業はほとんどないのも特徴です。
ぜひこの機会に福利厚生制度の拡充を検討していきましょう。